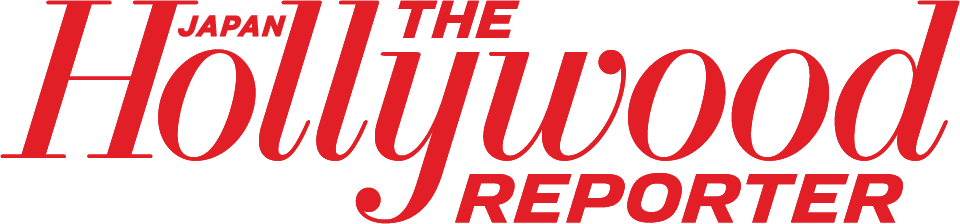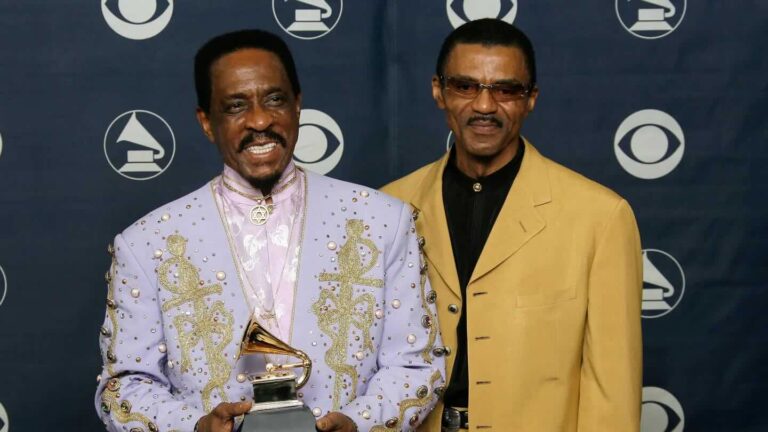ディズニー最新作 ウィン or ルーズ レビュー:1つを除いて素晴らしい作品

ディズニー作品といえば、象徴的な悪役や伝説的なヒーロー中心のストーリーが多い。Disney+(ディズニープラス)で配信中の『ウィン or ルーズ』は、これらの要素が驚くほど少ない。視聴者に視点を変えることで人間の捉え方がどのように変化するかを考えさせることを目的としている。いじめっ子だと思っていた教師も、よく知ることで優しい人に見えるかもしれず、誰かの目にクールな子たちが別の人から見ると嫌な奴らに見えることもある。
その基準で見ると、本作は成功していると言える。ピクサーのアニメーションは非常に美しく、画面越しにその明るさや質感を感じ取れるほど鮮やかだ。キャラクターたちは個性的でありながら親しみやすく、誰にでも共感できる。巧妙なストーリーテリング、物語のシーンや場面の細かな描写に引き込まれる。ディズニー作品らしさ、を感じるものだ。
「ホームランを打った」と言いたくなるほど素晴らしいディズニー作品だが、ひとつの重大な誤りが、明確な勝利であるべき作品に喪失感を与えている。
この『ウィン or ルーズ』の8つのエピソードは、ピックルズという若者の混成ソフトボールチームのメンバーやその周辺の異なるキャラクターに焦点を当て、それぞれが大事な試合を前にした1週間を描いている。クリエイターであるキャリー・ホブソンとマイケル・イエーツは、各登場人物に起こる出来事だけでなく、その主観的な感情体験がどのように感じられるのかを見せている。
例えば、12歳の外野手ローリーの不安は、肩に重くのしかかる灰色の塊として現れ、10歳のイラの白昼の夢は、子どもっぽいクレヨンで描かれたスーパーヒーローの漫画として表れている。これらは典型的なピクサーの演出であり(特に前者は『インサイド・ヘッド2』の一部のように感じさせる)、半時間の放送時間に合わせて巧みに表現されている。
これらの物語は総じてパズルのような形を成しており、あるエピソードで登場したマイナーなキャラクターが次のエピソードで主役となったり、物語を進めるための小道具が後のエピソードで背景に登場したりする。すべてが試合の前に起こる人生を変えるような出来事に向かって進んでいるように見え、オープニングの子どもたちや大人たちが叫ぶシーンには「アヴェ・マリア」が流れている。
物語的には少し賭けのような部分もある。5つのエピソードは、それぞれ感情のクライマックスに到達する直前で終わり、最終回でそれらの結末が一緒に描かれることを前提にしている。この方法は、ランダムな短編の寄せ集めに見えてしまう可能性のある物語に勢いを与える効果的な方法である。
『ウィン or ルーズ』の素晴らしいトリックは、この構造を使って視聴者に関心を引き寄せさせることである。ローリーの家が引っ越しの箱でいっぱいであること、でもそれが彼女の父親のためだけであることに気づかせようとしている。ロシェル(ミラン・エリザベス・レイ)が困窮するシングルマザーのヴァネッサ(ローザ・サラザー)に落胆する場面も、視聴者に気づいてほしい。さらに、コーチ(ウィル・フォーテ)による同じ励ましの言葉が、誰が聞くかによってどう違うかに気づかせようとしている。
そしかし、ディズニーがこの共感を制限する決断を下したことがは残念である。
昨年末に米『ハリウッド・リポーター』が報じたように、ディズニーは多くのピクサースタッフの反対を押し切って、トランスジェンダーのチームメイトであるカイ(シャネル・スチュワート)に関するストーリーを削除した。キャラクター自体は残ったが、カイを中心にしたエピソードが送られず、私たちが見たエピソードでも彼女は重要な役割を果たしていない。最後の瞬間の書き直しがどのように展開されるのか、彼女のアイデンティティがこの物語にどれほど重要であったのか、あるいはそれを消すことでどのように理解が変わるのかはわからない。
ただし、トランスジェンダーの子どもたちに対して、そして自分自身や愛する人々を見出す人々に対する少しの思いやりがとても大切だ。トランスジェンダーの子どもたちがケアと理解を受けるに値し、そしてそのことを強化するような物語が必要である。そして、このディズニーシリーズがその立場を取らなかったことは、それ自体がまさにこの作品の基盤として掲げていた思慮深い好奇心の精神と矛盾しているとも言える。
『ウィン or ルーズ』は多くの点で素晴らしい作品である。しかし、その作品を公開したディズニーが、最終的にその価値あるメッセージを生かせなかったことは残念だ。
本記事は抄訳・要約です。オリジナル記事はこちら。
【関連記事】
- ディズニー、国内初の特大オリジナルアートをイオンシネマ24劇場に提供へ
- アニメ界のアカデミー賞:2025年アニー賞受賞作品
- 【U-NEXT】2025年2月の配信作品:『ホワイト・ロータス』S3、『グラディエーターII』など話題作が登場!
- 東映、アニメ大作『ChaO』『ペリリュー』などラインナップ16本を発表
- Netflixが「マイメロディ」と「クロミ」を主人公にしたストップモーションアニメを制作 『My Melody & Kuromi』7月に配信