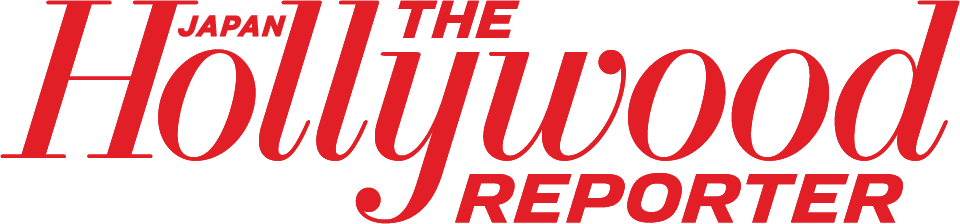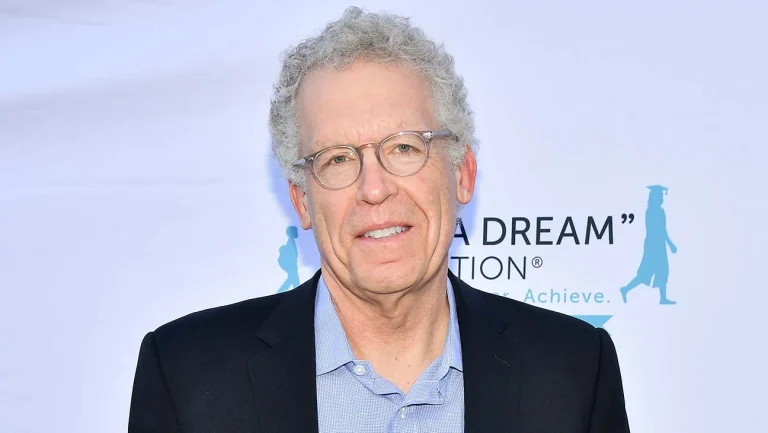かつてのカンヌを象徴する奔放さと華やかさ──写真で見るその終焉

1984年は、映画『パリ、テキサス』がカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞し、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』が世界初公開された年だ。そして、イギリスのストリートフォトグラファーであるデレク・リッジャーズが、初めてクロワゼット通りに足を踏み入れた年でもある。
このクロワゼット通りは、カンヌ映画祭の中心舞台でありながら、その過剰な華やかさ、パパラッチの群れ、自己演出に満ちた騒々しい光景で知られ、映画祭の狂騒と虚飾を象徴する“悪名高い”場所とされてきた。
当時のリッジャーズは、NME誌の仕事でアフリカ・バンバータの撮影と映画『ビート・ストリート』の上映取材のために現地を訪れていた。しかし、彼が出会ったのはまるで“サーカス”のような光景だ。
写真集『Cannes(カンヌ)』は、名の知れた人物から無名の者までを執拗に追いかけるアマチュア写真家たちの、滑稽さ、熱狂、そして奔放さを鮮やかに捉えている。

「このバカげたほどにクレイジーなサーカスにすっかり引き込まれた。しかも、あの光景がものすごく絵になると思わなかったと言ったら嘘になる」と彼は語っている。
1996年まで、リッジャーズはこれを毎年の恒例行事にし、有名人を追いかける写真家たちを撮影し続けた。時には、クリント・イーストウッドやミッキー・ロークといったスターたちが偶然フレームに収まることもあった。
この写真集は限定500部で、5月15日にオンラインのIDEAおよびDover Street Marketの全店舗(ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルス)で発売される予定である。ここでは、リッジャーズ自身が各写真の舞台裏について語っている。

year, very happy to pose for all the photographers.” Derek Ridgers
なぜ今、この写真集を出そうと思ったの?
この本の直前に出版した『London Youth Portraits』がおそらく自分にとって最後の“真面目なモノグラフ”になると思っている。45年も続けてきたのだから、少し肩の力を抜いてもいい頃合いだと感じている。

この写真集は、特に真面目な作品というわけではない。テーマは、1980〜90年代のカンヌ映画祭にあったクレイジーで楽しい時間だ。全体的にかなり気まぐれで軽やかなもので、そこに深い意味は込められていない。
本当に圧倒されるようなスターに出会った瞬間はあった?
いや、自分が映画スターや映画監督、ロックスターに特別圧倒されたことは一度もないと思っている。有名人と同じ部屋にいても、彼らは他の誰とも変わらない存在だ。よそよそしかったり、自惚れているように感じることもあるが、それは有名人に限った話ではない。写真家だってそうなのだから。

撮影にはどんなカメラを使っていた?
当時のお気に入りのカメラは、ニコンFM2だった。完全なマニュアル式のフィルムカメラで、電池を使うのは露出計だけ。そのぶん、故障の心配も少なかった。
しかも、炎天下でも息切れすることもなく、一日中2台持ち歩いていられるくらい軽快なカメラだった。

この中で最も気に入っている写真はどれで、なぜそれを選んだの?
この写真集の中で一番のお気に入りは、16ページにある、ストライプのコートを着た女性が看板の前でポーズをとっている写真だ。彼女を撮っているのはほんの数人で、大多数の人々はただ立ち尽くし、何かが起きるのを期待するように見守っている。
まさにカンヌという場の一面を象徴している。何かが起きていることは誰もが感じているが、実際に何が起きているのかは誰にもはっきりわからない。

この時代が終わったと実感したのは、どんな瞬間だった?
自分は「昔のほうが良かった」と口癖のように言う年寄りの一人ではない。今のカンヌ映画祭だって、当時と同じくらい楽しいはずだと思っている。太陽も、海も、ビーチも変わらない。映画スターの顔ぶれこそ違っていても、きっと数は変わらないだろう。
あの頃のように“狂気のダイヤル”が11まで振り切れることはないかもしれないが──いや、ひょっとすると今でもそうなのかもしれない。

カメラを取り出さなかったのは、どんなとき?
ジョン・ハートはカツラをかぶっていたせいでまったく別人のように見えたが、カンヌでは『Starlet』という映画のプロモーションをしていた。
当時、カンヌ期間中に毎日発行されていた2つの無料新聞では、この話題が大きく取り上げられていた。
もう一つの目玉は、丘の上にあるエレガントな別荘で開かれるというパーティだった。まさに自分が潜り込むべきパーティだと思った。
パーティ当日の夜、タクシーでその別荘へ向かった。しかし現地は完全に無人のように見えた。すでにタクシーは去っており、仕方なく玄関のドアをノックした。通されたのは、カンヌの湾が一望できる大きな応接室だった。

部屋にいたのは、自分以外ではジョン・ハートだけだった。今度はカツラを外していて、ソファに仰向けになり、大声で電話をしていた。彼はこちらを一切見ようとせず、自分の存在にまったく気づいていないかのようだった。
若い女性が白ワインをグラスに注いで差し出し、そのまま部屋を出て行った。それから約30分間、その部屋には自分とジョン・ハートの二人だけだった。彼は完全に自分を無視し、自分もまた彼を無視し続けた。とても気まずい時間だった。

やがて、あの若い女性が部屋に戻ってきて、少しずつ人が集まり始めた。そのパーティは、どうやら映画に出演している俳優や関係者だけのものだったようだ。ジョン・ハートを除けば、皆とても感じがよく、自分が誰なのか、なぜそこにいるのかを尋ねてくる者は一人もいなかった。
自分はカメラをバッグにしまったまま、取り出すことはなかった。結果的にパーティ自体は楽しいものになったが、最初の30分間はひたすら苦痛だった。IMDbによれば、ジョン・ハートが出演した『Starlet』という映画は存在しない。
もしかすると、すべては自分の夢だったのかもしれない。

本記事は抄訳・要約です。オリジナル記事はこちら。
【関連記事】
- カンヌ2025国際映画祭で公開、『リトル・アメリー』アニメーション予告編
- デンゼル・ワシントン主演『Highest 2 Lowest (原題)』予告編公開—黒澤明原作の再解釈がカンヌで初上映へ
- 【11作品厳選】プライムビデオで話題の新作映画を今すぐ視聴
- 【ディズニープラス】5月の新作ラインナップ発表『スパイダーマン』関連作品など
- 『ガンニバル』人喰い村を描いた物語が、いかにしてディズニープラスで日本最大の実写ヒット作となったのか?