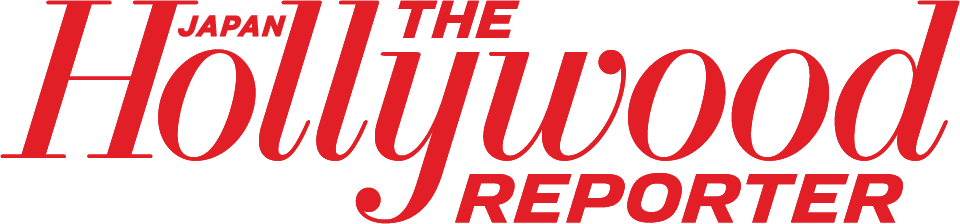『メイ・ディセンバー ゆれる真実』レビュー: ジュリアン・ムーアとナタリー・ポートマンの圧巻の演技

トッド・ヘインズ監督最新作『メイ・ディセンバー ゆれる真実』は、親密さや冷静さが絡み合った複雑なドラマ作品だ。これまでのヘインズ作品ではお馴染みの、自己認識とパブリックイメージ、社会規範と性的な道徳への反抗といった様々な対比は同作においても取り扱われている。しかしながら、そのアプローチが映画の感情の起伏を抑えてしまい、ヘインズの熱烈なファン以外には受け入れにくい作品となっている。
一方で、思惑が交差する2人の女性を演じたナタリー・ポートマンとジュリアン・ムーアの心をつかんで離さない演技が、今作を勢いよく引っ張っている。イングマール・ベルイマン監督『仮面/ペルソナ』に影響を受けたヘインズならではの、2人が目まぐるしく様々な一面をみせていく演技に釘付けになる。
今作が想起させるのは、ワシントン州の教師メアリー・ケイ・ルトーノーの事件だ。ルトーノーは、13歳の少年への第2級レイプで有罪となり、90年代後半にタブロイド紙でセンセーションとなった。その見出しには、“レイプ”や“ロマンス”といった言葉が並んだ。(ルトーノーと少年は同意の上での関係だったと主張)
ルトーノーと同じく、グレイシー(ジュリアン・ムーア)は30代半ばで、同僚だった13歳の少年ジョー(チャールズ・メルトン)とセックスしているところが見つかってしまう。服役中に1人目の子供を産み、その後グレイシーとジョーは結婚。彼らの事件は全米を騒がせ、その汚名から2人は隠遁生活を送っていた。やがてタブロイド紙にウェディング・フォトを売り、夫婦はジョージア州サヴァンナに家を購入。それから20年経った現在でも、嫌がらせ目的の郵便物が止むことはなかった。
俳優のエリザベス(ナタリー・ポートマン)は、映画でグレイシー役を演じることになり、グレイシーとジョーの人生を探るためサヴァンナにやって来る。グレイシーは、プロジェクトが世間に漂う噓の数々を訂正し、ジョーとの人生に対する権利が埋め合わせされることを望んでいると推測できる。しかし、グレイシーが激怒するシーンが何度も登場したり、過去を語りたがらないことを考えると、脚本には“どうして映画化権を認めたのか?”という説明が抜け落ちている。
序盤から、ヘインズは特に音楽を用いながら、一般人によってグレイシーとジョーの物語が解釈されていくさまを弄んでいく。時に、愉快なメロドラマ風にシーンを途切れ途切れにしたり、厳かなオープニングにはミシェル・ルグランが映画『恋』に提供した楽曲を使用している。
夫婦の自宅で行われたバーベキューで、エリザベスは初めて2人と対面することに。グレイシーをかばう友人は、優しく接するようエリザベスに釘をさす。当初は、グレイシーに対し踏み込んだ質問はせず、熱心にメモをとるエリザベス。しかし、ある2年間の期間について質問が及ぶと、グレイシーは身構えるようになる。その後も2人は交流を続け、エリザベスはグレイシーの最初の夫トムをはじめ、弁護士モリス、長男ジョージから話を聞き出す。
衣料品店のシーンで、店の鏡に映る2人のグレイシーに挟まれたエリザベスを捉えたショットは、撮影監督のクリストファー・ブローヴェルトの技量が光っている。娘のメアリーの体型に関する辛辣な言葉は、グレイシーの批判的な一面をあぶり出す。ムーアは、時にグレイシーが露にする手厳しい一面を見事に演じ切っている。
一方ジョーには、迫り来る子供たちの巣立ちや、エリザベスの存在によって浮かび上がる過去が重くのしかかっていた。グレイシーとは違い、過去の出来事を処理しきれていないジョー。製作陣は、グレイシーの行動を許容しない一方で、彼女を悪人として描いていない。しかし、ジョーの妻への接し方から、グレイシーが夫よりも上の立場にいることが仄めかされている。その暗示は、ムーアの卓越したセリフ回しからは感じ取りにくいが、夫婦の関係のはじまりの物語はグレイシーの手によって書かれたものだと考えられる。
過去にこだわらないグレイシーに対し、過去の選択や過ちを顧みることを有益だと考えるエリザベス。世間知らずだったかもしれないが、精神的に不安定というわけではなかった、とグレイシー本人は指摘しながら、自分の行為が過ちだったと完全には理解していないように思える。
この作品全体で、陰に潜んだモンスターはエリザベスだ。ポートマンは、キャラクターの洗練された対人スキルと貪欲な野心のバランスを見事に保っている。最初の方のシーンで、エリザベスはグレイシーとジョーの情事が暴かれたペットショップへと向かう。そこで彼女は駐車し、性の快楽を想像し身もだえする。まさにポートマンの主演作『ブラック・スワン』を彷彿とさせるシーンとなっている。今作にもっと生き生きとした部分があればと、観る側はこういったシーンをさらに求めるかもしれない。
最もショッキングな展開といえば、エリザベスが積極的にジョーの弱みに付け込もうとするところだ。まさに映画『ルームメイト』的な気味悪さを感じさせる。さらに恐ろしいことに、エリザベスは自分こそ上の立場にいる人間だとはっきりさせるのである。どうやら今作は、俳優の人間性を宣伝するのに最適なものではない。
メルトンはティーンエイジャーの面影が残った独特な美貌の持ち主で、非常にピッタリの役柄だ。一方で、いくつかの感情的なシーンでは、その技量に限界があった。そもそも、ポートマンとムーアの演技を超えられる若手俳優は多くない。グレイシーとジョーの結婚生活の中で爆発する大波乱によって、重大なダメージが示されてもなお映画は抑えが効きすぎていて、ドラマチックな満足感を得ることはできない。
主演俳優たちは映画の魅力を保ち続けているが、再び開かれた傷跡の生々しさを鑑みれば、すべてにおいて温度が低い。ブローヴェルトのカメラは豊かな緑を定期的に映し出し、そこでジョーは趣味で育成しているオオカバマダラ蝶の卵を採集する。これらのイメージは温室のような環境を暗示しており、作品にもっと効果的に用いることができたはずだ。
※今記事は要約・抄訳です。オリジナル記事はこちら。翻訳/和田 萌