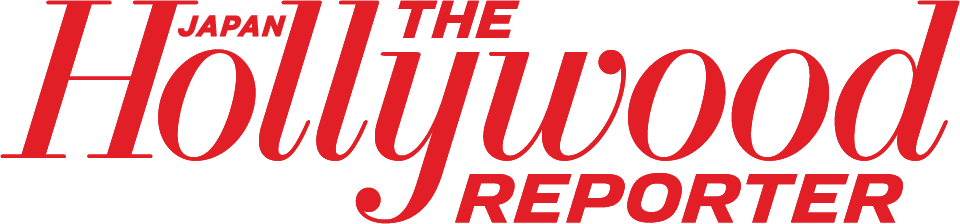カンヌ:ジュスティーヌ・トリエ監督が最新作「Anatomy of a Fall」の法廷でのフィクションとリアリティを語る

シャープさとニュアンスに富み、フェミニストの視点を取り入れ、新しいトゥルークライム映画の形を提示したフランス人監督・ジュスティーヌ・トリエの最新作「The Anatomy of a Fall」は、5月22日月曜日にカンヌ国際映画祭のコンペティション部門でワールドプレミア上映され、評論家と観客を魅了した。
本作は、2016年アカデミー賞ノミネート作品「ありがとう、トニ・エルドマン」で知られ、トリエ監督の2019年のドラマ「愛欲のセラピー」にも出演したドイツ人俳優サンドラ・フラーが、サンドラ・ヴォイター役で出演。ドイツ人の有名作家・サンドラは、フランス人で売れない作家の夫・サミュエル(サミュエル・タイス)を殺害した罪で、母国から離れたフランスで裁判にかけられる。この事件の唯一の目撃者は、11歳の盲目の息子・ダニエル(ミロ・マチャド・グレイナー)だった。
「氷の微笑」やHBOの「ザ・ステアケース -偽りだらけの真実-」のように、「犯人はサンドラなのか」というミステリースリラーを思わせる設定だが、トリエ監督の関心は犯人探しではない。検察が十分な証拠を持ち合わせていないとき、もっともらしい動機をでっち上げる法の仕組みと、動機を形成する保守的でときに性差別を含む思い込みに疑問を投げかけている。
アメリカの映画配給会社・Neonはカンヌ国際映画祭でのプレミアの直後、北米への配給を決定した。
米ハリウッド・リポーターはトリエ監督への取材を実施。現実に起きた犯罪の魅力、サンドラ・フラーに向けて書いた役の作り方や、スクリーンと法廷でのリアリティとフィクションの境界線ついて語ってくれた。
本作でサンドラ・フラーは素晴らしい演技を見せています。彼女を意識して役作りをしたのですか?
そうです。10年前、とある映画祭でサンドラから賞を受賞したのが最初の出会いでした。「ありがとう、トニ・エルドマン」を観ていたので作品はもちろん、女優としての彼女にとても感動しました。マーレン・アデ監督も大好きなので、たくさんのインスピレーションを受けました。だから、彼女のことはなんとなく頭の中にあったんです。それから「愛欲のセラピー」にも出演してもらいました。彼女にとっては小さな役でしたが、彼女と演技の関係性にすぐに共感したんです。彼女の演技へのアプローチはとても芸術的で、舞台からスタートし、体力的にもこだわりを持って自分のやることに取り組む彼女のスタイルは、フランスでは珍しいです。彼女のための役を作ろうというアイデアが生まれたのは、「愛欲のセラピー」の制作中でした。
当初のアイデアは、主に英語で書くというものでした。フランスに住むドイツ人作家というアイデアを思いついたのは、外国人の俳優と仕事をしたいからという単純な理由でなく、外国で裁判にかけられ、母国語で自分を弁護できない登場人物を描くうえで、言葉が核であるべきだと思ったからです。言語がプロットの重要な要素なんです。
この映画の構成はトゥルークライムの要素が多いですが、ファンなのですか?
制作にあたって、ほとんど毎日、現実に起きた犯罪の話を読んだり、裁判映画やドラマを観ました。私自身、裁判をテーマにした映画をいつか作ろうと思っていました。しかし、見た作品のほとんどは、ストーリーが簡単すぎてバレバレという印象を受けるものが多く、いつも簡単に事件が解決されてしまう。ネタバレになることはあまり言いたくありませんが、この映画はそうではありません。ストーリーが複雑で映画の終わりまではっきりわからないものを作ることが、この映画を作る意図でした。事件や裁判に関する疑問が絶えず生まれるようにすることは、共作した脚本家のアルチュール・アラリと共に、強く意識した部分でもあります。犯人探しの映画として見ることもできますが、主に夫婦関係を描いた映画だと思います。私の関心は、殺人裁判という口実を使って、子供がいながら共通の言語を持たない夫婦の関係性に迫ること。それがメインのストーリーであり、裁判はサイドストーリーに過ぎません。
リアリティとフィクションの問題、そして現実世界の事実をどのように物語に変えていくかが、この映画の核となるテーマであるように思います。二人の作家は、実生活をネタに小説を書く、半自伝的な作品を仕事にしています。そして、検察側と弁護側の弁護士がそれぞれ、とても曖昧な事実から異なる架空のフィクションを作り上げる法制度も映画に登場します。
まさに。裁判所は私たちの人生がフィクション化され、ストーリーや物語が付け加えられる場所だと思います。裁判所では誰もが作り上げた物語を語り、全てが真実から遠くかけ離れています。彼女の罪の立証を試みる相手の検察官と同じように、サンドラと弁護士でさえ、彼女を弁護するために現実を歪めてしまうのです。司法は、彼女の生き方に対して一方的な判断をします。この作品のリサーチを進めるうえで興味深かったのは、2023年の今日でさえ、少なくともフランスをはじめとする欧米諸国では、女性が男性と同等の地位であるはずなのに、職業選択や性自認といった人生の選択が否定的に判断されてしまうことです。バイセクシュアルであるサンドラも、裁判では不利な立場になってしまいます。このような裁判がある意味、人々にとって悪夢であることを示したかったんです。誰もがフィクションを作り上げ、真実に目を向けようとせず、自分の人生が奪われてしまう。物語を通して真実を追い求める者として、とてもおもしろかったです。
夫婦喧嘩を録音した音声は物語の核となる要素の一つであり、裁判で重要な役割を果たします。最近では録音データは絶対的な証拠として扱われますが、検察官の脈略のない使い方で、サンドラをストーリーをでっち上げ、攻撃するための材料になってしまいます。誰もが実際に起こった真実を完全に切り離し、ありもしないフィクションを作り出しているんです。
録音はどのように行われたのでしょうか?撮影現場で録音したのですか?
夫婦喧嘩の撮影には2日かかり、かなり大変でした。最初の脚本を書く段階から共作した脚本家と意見が割れていて。喧嘩のシーンを書くために、脚本家同士でその意味について喧嘩したんです。サンドラは1日で全部のシーンを録りたくて、途中で止めるのは嫌だった。でも、本当に過酷で大変な作業だったんです。そこで、初日に撮影をしました。ビジュアル的に必要な素材は全て揃っていたものの、夫婦役の俳優2人が最後まで演じるまでやめられなくなっていることに気づき、録音を続け、12〜14分くらいの長さかと思いますが、最後に暴力的な結末で終わるまでの全てのシーンを録音しました。もともと音に興味があったのでとても有意義な経験になり、視覚的な映像よりも音にもっとこだわるようになりました。映像のように音はごまかすことはできないからです。真実は音にあると思います。犯罪の話や裁判に見られるものですが、観客は音に魅了され信憑性を感じることができます。さらにもうひとつ、映像では決して作り出せない、音から感じる感情の力やメランコリーさという側面もあります。この映画を作るうえで、脚本段階から決まっていたことの一つは、映像を使わず音だけのシーンを作ることです。音は、物語の真実を求めるうえで大事な材料になります。
時間が迫ってきているので、最後に肝心な質問を一つ。作品に登場する犬、ボーダーコリーのスヌープは、プロットの中で重要な役割を担っています。個人的に彼は今年のカンヌ国際映画祭のパルム・ドッグ賞の最有力候補ですが、スヌープとの仕事は大変でしたか?また、どのように物語に組み込んだのですか?
スヌープが夫の代わりだということは最初から明らかでしたが、彼は単なるキャラクターでも、ただ走り回っている動物でもないんです。いろんな意味でスヌープは、死んだ人やいない人の象徴です。最終的にカットしてしまったのですが、スヌープが嘔吐するシーンがあり、彼がサミュエルに取って代わった存在であることを象徴するものでした。以前にも犬や猿が登場する作品を撮影したことがあるので、動物と仕事することの大変さはよくわかっています。しかし、今回は幸運なことに、動物を訓練している方と一緒に仕事ができました。スヌープが人間のキャラクターと同じくらいの役割を担うためには、スヌープのオーナーの女性は本当にいなくてはならない存在でした。事実、犬の目線になってスヌープの視点から物語を見るシーンがいくつかあります。彼が人間と変わらないキャラクターであることが、私にとってとても重要なことでした。
※オリジナル記事はこちら。