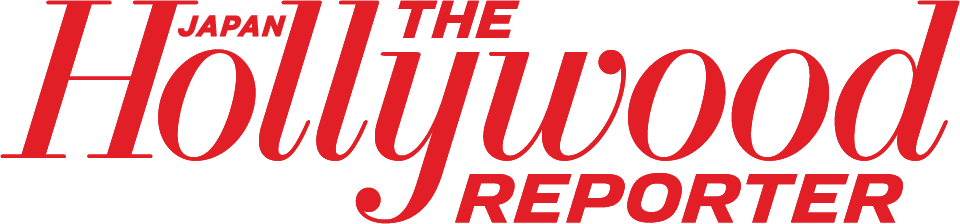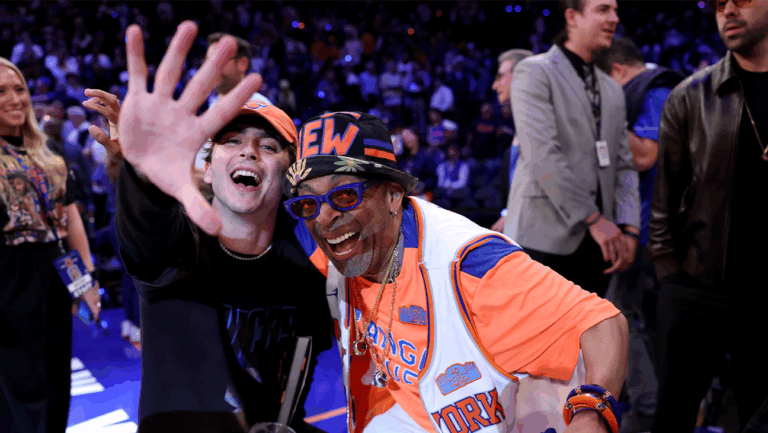吉沢亮×横浜流星『国宝』を徹底解説|歌舞伎と宿命の物語

[本記事は、映画『国宝』の重大なネタバレを含みます]
※本記事で紹介した商品を購入すると売上の一部がTHE HOLLYWOOD REPORTER JAPANに還元されることがあります。
歌舞伎の宿命と芸の系譜を描く壮大な叙事詩
『国宝』は、歌舞伎という閉ざされた世界を舞台にした同名小説に着想を得た作品であり、そのタイトルが示すとおり、重厚な物語のスケールを誇る。物語は1960年代半ばに始まり、半世紀にわたる時の流れを描き出す。日本の近現代史を背景にしながらも、説明的になることなく、その空気を繊細に織り込んでいる点が印象的である。

大ヒットロングラン上映中!
ナレーションは尾上菊之助
監督は李相日。彼の演出はオペラのような情念と映像詩的な美しさに満ち、3時間に及ぶ長編ながら、観る者を強く引き込む力を持っている。その密度と情感は圧倒的だ。物語の中心にあるのは、2人の俳優の対照的な人生である。ひとりは歌舞伎の家系に生まれた者、もうひとりは外の世界からこの伝統芸能に挑む青年だ。2人の道が交錯する中で、作品は舞台裏のメロドラマ、継承の物語、そしてひとりの芸術家が生まれるまでの過程を見事に融合させている。

主演の吉沢亮と横浜流星は、舞台上と舞台外の二面性を見事に体現し、繊細で奥行きのある演技を見せる。その演技は、役者という存在そのものの葛藤と輝きを体現していると言える。
李監督の到達点――「芸」に宿る人間の真実を描く
李監督にとって本作は、『悪人』(2010年)、『怒り』(2016年)に続く吉田修一原作の3作目の映画化である。『国宝』は日本代表としてアカデミー賞国際長編映画賞部門への出品が決定しており、アメリカではAFIフェストで初上映された後、11月中旬から限定公開が始まる予定だ。

伝統と宿命のはざまで――「女形」という存在の美と哀しみ
本作の脚本を手がけたのは奥寺佐渡子。李監督は、彼女の脚本をもとに、歌舞伎における「女形(おんながた)」——17世紀、将軍によって女性の舞台出演が禁じられて以来、女性役を演じ続けてきた男優たち——に焦点を当てている。物語の中では、この伝統そのものが問い直されることはない。フェミニズム的な視点も、制度批判もない。ただひたすらに、その技と魂を極めようとする姿勢、そして女形という芸の尊厳が描かれるだけである。
『国宝』が照らし出す二面性は、社会的な制度ではなく、登場人物たちの生き方そのものに宿る。タイトルの「国宝」は、まさにその象徴だ。劇中で、ある人物が女形を指して「彼は死んだら芸しか残さない」と語る場面がある。その言葉には哀しみがにじむが、同時にそれは最高の賛辞でもある。李監督と奥寺は、この「芸にすべてを捧げる」という生き方を、悲劇としても美学としても描いている。
作品はまた、俳優という存在の虚栄と献身にも目を向ける。ある登場人物が彼らを「欲深い生き物」と評するように、役者は常に承認を求め、光を渇望する存在である。しかし同時に、彼らは観客のために自らを削り、人生のすべてを舞台に捧げる。それが『国宝』と呼ばれるに値するゆえんであり、李監督が本作を通じて称えようとしたものなのだ。
雪の夜に始まる――運命の幕開け
物語の幕が上がるのは、長崎に珍しく雪が降る夜である。その静謐で幻想的な光景は、やがて作品全体を貫く印象的なモチーフとなる。李監督はこの雪を、記憶と宿命、そして芸の純粋さを象徴するように巧みに織り込んでいる。
物語の序盤では、後に吉沢亮と横浜流星が演じる2人の主人公が、まだ少年だった時代が描かれる。登場から約40分、彼らの若き日を演じる黒川想矢と越山敬達が、鮮烈な存在感を放つ。2人の演技は繊細でありながら力強く、彼らの人生を形づくる「芸」と「出会い」の瞬間を見事に体現している。
新年を祝う宴席の場面では、長崎のヤクザ(演:永瀬正敏)の屋敷に、名歌舞伎俳優・花井半二郎(演:渡辺謙)が招かれる。渡辺謙は『怒り』(2016年)や『許されざる者』(2013年)でも李監督作品を支えた俳優であり、その存在感は本作でも圧倒的だ。宴の席で、14歳の息子・喜久雄(演:黒川想矢)が女形として披露する舞に、花井はただならぬ才能を見出す。この出会いこそが、のちに喜久雄を芸の道へと導く、決定的な転機となる。
復讐の果てに見出す、芸への道――少年・喜久雄の旅立ち
物語は1年後、悲劇の連鎖とともに再び動き出す。父親が殺され、復讐を試みたものの果たせなかった喜久雄は、闇の世界に足を踏み入れかけていた。喜久雄を救おうとする継母・立花マツ(演:宮澤エマ)は、少年の未来を犯罪の世界から遠ざけるため、花井半二郎のもとへ弟子入りさせる決断をする。花井は名門・丹波屋の血筋を継ぐ歌舞伎俳優であり、現在はその家を率いる存在である。
花井の妻・幸子(演:寺島しのぶ)は、当初こそ少年の素性に警戒心を抱くが、やがて喜久雄を実の子のように迎え入れ、厳しくも温かい眼差しで育てる決意をする。幸子の母性と誇りが交錯する姿は、物語に静かな深みを与えている。なお、喜久雄がぽつりと漏らす「実の母は原爆症で亡くなった」という言葉が、戦後の傷跡を静かに響かせる。
幸子の息子・俊介(演:越山敬達)は、喜久雄と同じ年齢で体格もよく似ている。だがひとつだけ異なるのは、喜久雄の背に刻まれたフクロウの刺青が、その過去と生き様を雄弁に物語っていることだ。2人の間には兄弟のような絆と火花を散らすライバル心が、同時に芽生える。花井の厳格な指導の下、彼らは互いを刺激し合いながら、芸という過酷な道を歩み始める。
芸に命を懸ける修行――暴力と愛情の狭間で
花井半二郎の指導は、現代では到底許されないほど苛烈なものである。肉体的にも精神的にも容赦がなく、罵声と叱責が飛び交う稽古場であり、1965年当時ですら眉をひそめる者がいたほどだ。だが、喜久雄はその厳しさの裏にある真意を感じ取り、痛みをものともせず稽古に打ち込む。喜久雄にとって花井は「最高の師」であり、あざさえも勲章のように感じている。
やがて花井は、孤児であり、元ヤクザの息子でもあるこの少年に「花井東一郎」という芸名を授け、自らの一門である丹波屋の系譜に迎え入れる。その瞬間、喜久雄は過去の影から抜け出し、芸の血脈に生まれ変わるのだ。だが、妻の幸子はその決断を複雑な思いで見つめる。幸子は、喜久雄が天賦の才を持つのか、それとも俊介をしのぐ野心だけで駆け上がろうとしているのか、判断しかねていた。後に幸子は喜久雄を「汚れた泥棒」と罵るが、その言葉には愛憎が入り交じっている。
花井が見抜いたのは、喜久雄の才能だけではなく、どんな屈辱にも屈しない胆力である。しかし、芸の道は決して平坦ではない。この少年はこの先、栄光と破滅の狭間で己のすべてを賭けることになる。
美と芸の狭間で――青年たちの光と影
物語の転機となるのは、ひとりの老女形との出会いである。伝説的な女形・万菊(演:田中泯)が喜久雄に「おまえの美しさは、芸の妨げになるかもしれぬ」と告げる。その言葉は警告であると同時に、芸に生きる者への予言のようでもある。舞台上で万菊の姿を目の当たりにした喜久雄は、まるで悟りを開くかのような衝撃を受ける。その瞬間、少年期の章が静かに幕を閉じ、物語は1972年へと跳躍する。
時は移り、喜久雄と俊介はそれぞれ吉沢亮と横浜流星によって演じられる青年へと成長した姿が描かれる。2人は長年、女形として共に修練を重ねてきた。舞台では、藤の花をモチーフにした「二人藤娘」といった演目で、伝統的な化粧と華麗な衣装をまとい、まるでシンクロナイズドスイマーのような完璧な呼吸と動きで観客を魅了する。
だが、その華やかな舞台の裏では、早くも小さな亀裂が生まれていた。花井の反対を押し切り、後援企業の重役(演:嶋田久作)が2人を大劇場に出演させたことで、彼らは「2人の女形」として一躍スターにのし上がる。アイドル的な人気を得たその姿は、まるで歌舞伎界のボーイズ・デュオのようだ。
しかし、舞台を降りた2人の歩幅は次第にずれ始める。俊介は宣伝や後援者との付き合いに敏感で、芸以外の世界にも適応していく。一方、喜久雄――いや、花井東一郎は、己の芸にすべてを注ぐのみで、周囲の喧騒を意に介さない。やがて俊介は、自分には藤一郎ほどの天賦の才がないのではないかと気づき、静かに焦燥を募らせていくのだ。
芸に恋した男――愛と犠牲のはざまで
藤一郎(喜久雄)の恋人・春江(演:高畑充希)でさえ、藤一郎の心を完全に奪うことはできない。藤一郎の中でもっとも強く燃えているのは、人への愛ではなく、芸への執念そのものだからだ。春江もまた、それを痛いほど理解している。
やがて「曽根崎心中」の舞台で藤一郎が主演の女役を務める夜、客席には春江と俊介の姿があった。2人は離れた席からその舞台を見つめながら、藤一郎がいままさに人生の転換点を迎えていることを悟る。舞台上では復讐と絶望、そして慟哭が交錯し、観客を圧倒する。だが舞台裏では、その芸の頂点を見届ける2人の心が静かに揺れている。芸に生きる者の歓喜と、藤一郎を愛する者の孤独が同時に刻まれるこの場面は、映画全体の中でも最も強烈なシーンのひとつだ。
脚本の精密さと感情の揺れ幅は見事であり、俊介が涙ながらに「俺は本当の役者になりたい。偽物じゃなく」と語る台詞は、俳優という存在の核心を突いている。編集を手がけた今井剛の手腕も冴えわたり、舞台と現実を滑らかに行き来させながら、観る者の心を深く揺さぶる。
舞台美と映像詩――時代を超えて紡がれる芸の美学
美術監督の種田陽平(『キル・ビル Vol.1』『思い出のマーニー』)は、半世紀にわたる物語の中で、時代ごとに息づく生活空間を丹念に再現するだけでなく、歌舞伎舞台ならではの様式美と華麗な人工性を見事に造形している。その緻密なデザインは、現実と虚構の境界を曖昧にし、作品全体に独特の艶やかさを与えている。
衣装デザイナーの小川久美子による装いもまた、登場人物の内面を映し出す。舞台用の豪華絢爛な衣装に加え、普段着にさえキャラクターの心情が宿る。なかには、舞台上での「早替わり」を前提に仕立てられた衣装もあり、衣装そのものが演出の一部として息づいている。
撮影を担当したのは『アデル、ブルーは熱い色』(2013年)で知られるソフィアン・エル・ファニ。光と質感の対話を捉えるその撮影は、歌舞伎役者たちの顔に寄るクローズアップで真価を発揮する。仮面のような白塗りの奥に潜む感情を、静かに、しかし確かに浮かび上がらせている。音楽は原摩利彦(はら まりひこ)。オーケストラの高鳴りと、静謐なミニマルサウンドを行き来しながら、物語の抒情を精緻に支えている。

物語が時代を進めるにつれ、ドラマはしばしば過熱し、後半では展開の急旋回にやや驚かされることもある。しかし、その予測不能さこそが本作の魅力でもある。喜久雄と俊介、そして彼らを取り巻く人物たち、誰ひとりとして予定調和の人生を歩まない。その象徴が、当初は藤一郎(喜久雄)を軽蔑していた実業家(演:三浦貴大)が、やがて思わぬ形で彼の味方となるエピソードである。
芸に生き、芸に呑まれる――人間としての儚さと美しさ
物語が進むにつれ、登場人物たちはそれぞれに試練と栄光、そして転落を経験していく。しかし、主演の2人――吉沢亮と横浜流星――は決して揺るがない。吉沢が演じる藤一郎は、芸に取り憑かれた男である。芸者(演:見上愛)との間に子をもうけながら、その存在をほとんど顧みず、やがて大物歌舞伎役者・吾妻千五郎(演:中村鴈治郎)の娘・彰子(演:森七菜)と、打算を感じさせる恋に踏み出す。
だが吉沢の演技は、決して単純な嫌悪や同情を誘わない。その内面には、理解不能なほどの情熱と孤独が渦巻いている。観客は彼を非難もできず、完全に理解することもできない――その曖昧さこそが魅力である。
一方、花井を演じる渡辺謙は、芸の権威としての重厚さと、人間的な欠落を併せ持つ師の姿を圧倒的な存在感で体現する。花井は喜久雄に「芸を極めることこそが、おまえの甘美な復讐だ」と語りかける。その言葉が示すように、『国宝』は単なる芸道の物語ではない。名誉と忠誠、誇りと贖罪――まるで任侠映画のような「掟の世界」に通じる情念が、そこには脈打っている。
だがもっとも息をのむのは、吉沢と横浜による女形の舞台演技である。力強くも優雅な所作、儀式のように研ぎ澄まされた「女」という象徴の表現。その姿は現実を超えた幻のようであり、同時に、ただの人間としての脆さをあらわにする。彼らが演じるのは、芸術の神に身を捧げた「兄弟」であり、儚くも美しい人間の真実なのだ。
映画『国宝』は、大ヒットロングラン上映中!
※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。

【関連記事】
- 映画の原作を今すぐ体験!Kindleで読むべきおすすめ名作コミック&小説特集『国宝』『三体』、注目の新作映画まで
- 山田洋次監督、第38回東京国際映画祭で特別功労賞を受賞
- 【東京国際映画祭】世界が注目した名場面を厳選|レオナルド・ディカプリオも来場
- 李相日監督『国宝』カンヌ上映で歌舞伎を世界に発信「込めたものが全て届いている」
- 映画『国宝』なぜここまでヒット?興収150億円・1,000万人動員の理由