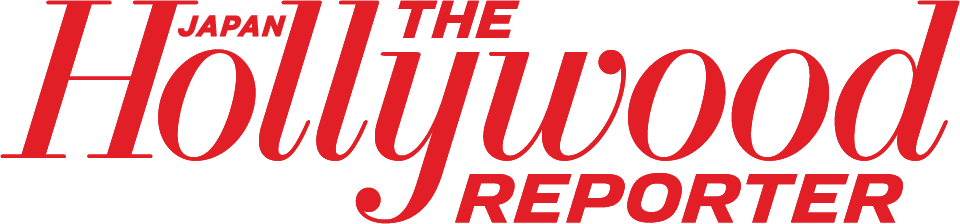映画『アンティル・ドーン』レビュー:人気ゲームをもとにしたサバイバルホラー

ホラーゲーム『Until Dawn -惨劇の山荘-』を映画化した『アンティル・ドーン/Until Dawn(原題)』は、原作のスリリングな要素を活かしながらも、その魅力を十分に引き出せていないホラー作品である。
森の中の廃墟となったビジターセンターを舞台に、5人の若者たちが繰り返される死と復活の悪夢に囚われるストーリーは一見興味深い。しかし、デヴィッド・F・サンドバーグ監督は、このループ設定をうまく活用できず、観客に散発的な恐怖感と漠然とした不満足感を残す結果となっている。
脚本を手がけたのは、ブレア・バトラーとゲイリー・ドーベルマン。ゲーム原作映画が乱立する中、本作もまたその一つとして登場したが、2025年4月に公開された『マインクラフト/ザ・ムービー』のような大ヒットには至っていない。とはいえ、2015年発売のゲーム『Until Dawn -惨劇の山荘-』が持つカルト的な人気は未だ根強く、本作にも一定のファン層が期待を寄せていた。
ストーリーの中心となるのは、母親の死と姉の失踪を経験したクローバー(エラ・ルービン)である。彼女の友人たちは、彼女を癒そうと“思い出の場所”を巡る旅に誘うが、途中で立ち寄ったガソリンスタンドから悪夢のような一夜が幕を開ける。
サンドバーグ監督は、床板の軋みやページをめくる音といった繊細な音響演出で緊張感を演出する。しかし、肝心のスラッシャー登場シーンは淡白で、期待された恐怖感が薄れてしまう。さらに、5人の若者たちが一度殺されても再び目覚めるという設定は、一見斬新だが、結果としてストーリーの焦点をぼやけさせる要因となっている。
廃墟の鉱山町という不気味な舞台設定には美術デザイナーの手腕が光るが、強烈なビジュアルも、構想の破綻やキャストの不安定な演技には勝てない。ゲームの心理的ホラー要素を再現しようとする試みも見られるが、結果的に“何でもあり”の展開がトーンの一貫性を欠いてしまっている。
総じて、『アンティル・ドーン』はゲーム原作映画としての期待を裏切る仕上がりとなった。サバイバルホラーとしての面白さは一部で発揮されているものの、ジャンルミックスの試みが作品全体の方向性を曖昧にしてしまっている。ゲームファンにとっては物足りなさが残る一作である。
映画『アンティル・ドーン』は米国で2025年4月25日に公開。
この記事は要約・抄訳です。オリジナル記事はこちら。
【関連記事】
- 【ホラー映画各ジャンル】恐怖の種類と魅力・おすすめ作品を紹介
- 恐怖の実話!本当にあった出来事を基にしたホラー映画11選
- ホラー界の気鋭映画監督が選ぶ、“最恐”の名シーン6選 ― あの日本作品も!
- 2025年公開予定の注目新作映画を一挙紹介!
- 『死霊館』シリーズ最新作、2025年9月全米公開へ ― 第4弾でついに完結