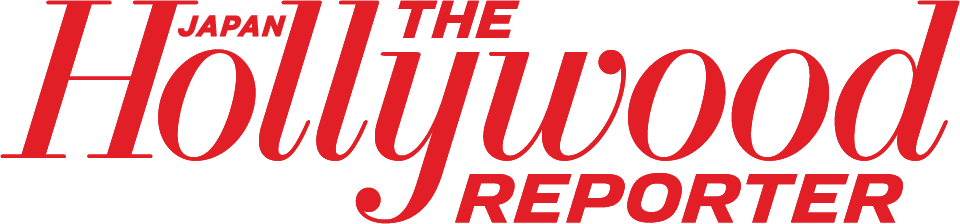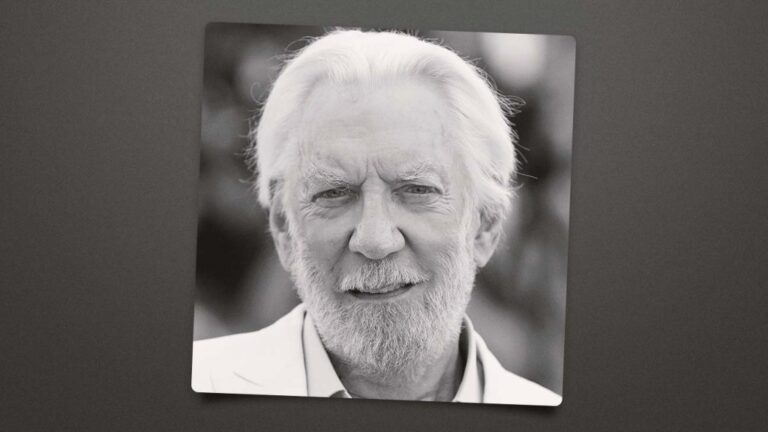ジェニファー・ローレンス、新作『Die My Love』で見せた“最も生々しい演技”の裏側 ── 作品の公開は「自分の日記を破かれるよう」

オスカー俳優のジェニファー・ローレンスは、『ハンガー・ゲーム』や『世界にひとつのプレイブック』など数多くの作品で大規模なプロモーションを経験してきた。しかし、リン・ラムジー監督の新作『Die My Love(原題)』について語ることは、これまでのどの作品とも異なる難しさを伴っているという。
『Die My Love』は、孤立した土地で心の均衡を失っていく母親の姿を描いた作品であり、ローレンスはこれまでで最も生々しく大胆な演技に挑んでいる。撮影時には第2子を妊娠中で、のちに産後うつとも向き合っていたことから、作品は彼女自身にとって極めて個人的な体験と結びついているのだ。
作品は今年のカンヌで初上映され、配給権は高額で取得されるなど、すでに大きな注目を集めている。11月7日にはついにアメリカで劇場公開され、来年の賞レースでも有力視されている。
以下、ローレンスは米『ハリウッド・リポーター』とのインタビューで、映画業界に対して不安に感じていることや、高い評価を得ている新作『Die My Love』との向き合い方、そして現在のプロモーション活動で直面している葛藤について率直に語った。
**
▼ジェニファー・ローレンスが語る新作『Die My Love』

■撮影の背景…名匠リン・ラムジーとのコラボレーション
――新作『Die My Love』で創作パートナーとなったリン・ラムジー監督についてお聞かせください。彼女は独自のビジョンを持つ監督ですが、あなたの演技はこれまでで一番、生々しい感情が表れていたように思います。
作家性の強い監督と仕事をするときは、実際にどんな現場になるかはやってみないとわからないものです。私は最初、彼女はすごく細かくコントロールするタイプだと思っていたのですが、実際はまったく逆でした。とても感情に導かれるタイプなんです。
撮影の数週間前に、私たちはカナダのカルガリーに集まって、キャラクターについて長い話し合いをしました。リハーサルというより、本当に会話のような感覚でしたね。そして彼女が撮影を行う家を案内してくれたのですが、家自体がもうひとつのキャラクターのように感じられてくるんです。彼女は世界観の構築をとても丁寧に行うので、いざ撮影に入る頃には、彼女は少し引いた位置に立ち、観察するようなモードに入ります。
でも、彼女は撮影監督としての側面もあって、構図のセンスが本当に卓越しているんです。どのショットを切り取っても、まるでウィリアム・エグルストンの写真みたいに見えるほどの才能があります。
――制作過程で驚いたことはありますか?
今回使ったのはとても珍しい種類のフィルム(Kodak 35mm Ektachrome)で、もう市場に残っていない可能性があります。もしかしたら、私たちが最後の在庫を使ったのかもしれません。まあ、そこは事実確認してくださいね(笑)。
それから、撮影監督のシェイマス・マクガーヴェイは、レンズ前のガラス部分を焼くことで独特の質感を生み出していました。また、「アメリカの夜」という、昼間に撮った映像を夜のシーンとして見せる手法も多く使いました。私がそれを最後に経験したのは『ウィンターズ・ボーン』のときです。その方法だと、画面の粒子感や雰囲気をより繊細に調整できるんです。
――夫役のロバート・パティンソンと共演してみて何か意外な点はありましたか?

意外というより、思っていた通りの人で、すごくホッとしたという感覚です。とても肩の力が抜けていて、優しくて、面白い人です。私たちは黙って一緒にいられました。それは私にとってすごく大事なことなんです。お互いにスマホをいじりながら、特に話さず、ただ一緒にいられる。共演者として本当に必要なことだと思います。
――特に本作のような映画では、なおさらですね。
1日15時間撮影していたんですから――話すことなんて尽きてしまいますよ。
■プロデューサー・役者としての視点
――カンヌでのプレミア後も、リン監督は本作の編集を続けていたと報じられています。プロデューサーと俳優という両方の立場から、そのことについてどう感じていましたか?
私は、原作と監督を結びつけ、資金調達を行ったことでプロデューサーになりました。監督と予算が確定したあとは、リンが必要とする創造的な自由を確保することが私の唯一の役割でした。つまり、基本的には彼女の邪魔をしないこと、そして周囲の誰からもその邪魔が入らないように守ることでした。
(再編集に)驚きはしませんでした。多くの監督は、誰かが物理的に編集室から引き離すまで編集を続けるものです。特にリンのようなタイプはそうです。今回、カンヌに間に合わせるために非常にタイトなスケジュールで編集を行いました。撮影したのは昨年の10月ですから、本当にスピード勝負でした。そもそもカンヌに出せる状態にまで仕上げたこと自体、彼女の力量の証だと思います。だから、もっと時間をかけたいと思うのは自然なことでした。
――これまで、『Die My Love』を何回観ましたか?また、自分の出演作を観ることについては、どのように受け止めていますか?
10回くらいだと思います。(出演作を観ることは)平気です。もちろん、自分の毛穴が気になったり、むくんでいるなと思ったり、想像がつくようなことはあります。でも、それが作品を観るうえで邪魔になることはありません。長くやってきたので、ある程度客観視できます。それに、ときどき自分で再生して確認したくなることもあります。監督の意図がつかめず、テイクを重ねすぎていると思ったときなどは、再生してみると理解が進んで助かるんです。
■キャラクターの苦しみと自身の感情が重なる瞬間
――『Die My Love』の原作に初めて出会ったとき、あなたは「自分は暗い場所にはいなかった。もし暗い状態だったら、この映画を作るのが怖すぎたかもしれない」と語っていました。その点について、もう少し聞かせてください。
私は、仕事を通して感情的な傷を癒すことがよくあります。どのキャラクターにも、自分の子ども時代の一部や、観察したこと、考え方など、どこか自分自身のかけらが入っています。それは私が感情を処理する方法でもあります。ただ、すでに自分の中で消化されているものを扱う方が、私には助けになるんです。
もし、この映画と重なるような暗い状態にいたとしたら、きっと私は避けていたと思います。想像するだけでも痛みが強すぎたでしょうし、まして現場でその感情を呼び起こすなんてできなかったと思います。でも、そのときの私はそういう場所にはいなかったので、作品の奥にあるものを落ち着いて見つめ、深く潜り込むことができました。痛みから逃げようとしていたわけではなかったんです。
実際に私が本格的な産後うつに苦しんだのは、2人目の子どものときでした。そして第2子を妊娠していたのが、まさにこの映画の撮影中だったんです。だから、より奇妙だったのは、産後うつと向き合っている最中に、この映画を観なければならなかったことです。本当にジェットコースターのような経験でした。

――親としての段階が変化するなかで、本作と向き合ったということですね。制作時と鑑賞時で、まったく違う状況だったわけですから。
本当にそうなんです。妊娠している状態で撮影することは分かっていましたが、ここまで多層的な経験になるとは思っていませんでした。いろいろな時期に観返すことで、毎回違う解釈や感情が生まれましたし、そのたびに作品の印象も変わっていきました。
――産後うつと向き合っている最中にこの映画を観たとき、どのように受け止めましたか?
撮影時には、まだ自分自身は産後うつを経験していませんでした。私は「子どもを産んだばかりの母親の死因の第1位が自殺である」という事実は知っていましたが、作中の彼女が自殺するという可能性は想像できませんでした。なぜなら、彼女は赤ちゃんをとても愛しているからです。私は「森は浄化的な意味を持っているのかもしれないし、再生の印なのかもしれない。自殺かどうかはわからない」と思っていました。
でも実際に自分が産後うつを経験したとき、「これは赤ちゃんをどれだけ愛しているかとは関係ない」とわかったんです。むしろ、その“深い愛”があるからこそ、自分の未熟さや不完全さが痛いほど浮き彫りになる。「私がこの子にとって唯一の欠けた部分になってしまう」という感覚です。そこから、「ああ、彼女は自分を追いつめてしまうんだ」と理解しました。
――本作への出演を通して、非常に大きな気づきがあったのですね。
撮影中は、すべてが“現実”でなくてはなりませんでした。意識していたわけではないのですが、ラキース(・スタンフィールド)演じるカールとの関係も、森の存在も、すべてが“彼女にとっては本物”でした。撮影中は、それが本当かどうか疑う必要がなかったんです。ですが、何度か映画を観るうちに「あれは実在しないものだったのかもしれない。彼女の想像が作り出したものだったのかもしれない」と思うようになりました。

■「自分の日記を見られるような気分」―― 作品との距離感
――ここ数か月、映画のプロモーションを続けていく中で、リン監督やロバートが本作について語るのを聞いてきたと思いますが、それはあなた自身の作品への理解にも影響しましたか?
映画というのは、いくつもの“別の映画”が存在するところが面白いと思うんです。まず作品そのものがあって、次に撮影中の映画があり、編集段階でまた違う映画になり、さらに観客として観る映画があり、そしてそれについて語るときにも新しい映画になる。今回はとても不思議な体験でした。
この映画はとても個人的で、内面的なものなので、いつか多くの人が観て語ることになるのが、どこか“侵入される”ような感覚があるんです。でも、リンの話を聞くと毎回新しい発見がありますし、彼女の話なら1日中聞いていたいと思うほどです。
――早い段階でプレミアが行われると、公開までの期間が長くなり、作品から離れるのが遅くなりますよね。その時間をどう感じていますか?
先ほど言ったように、すごく“侵入されるような感覚”なんです(笑)。これが映画制作の普通のプロセスだなんて、今でも信じられない。まるで、自分の日記をみんなに破かれて見られるような気分です。非常にパーソナルで、不思議な感じです。でも同時に、感謝の気持ちでいっぱいで、みなさんに観てもらうのが楽しみでもあります。
――俳優からプロデューサーに立場が広がると、作品のレビューを意識するようになったという声もあります。あなたはレビューを読むようになりましたか?
読みません。必要なことがあれば、チームが教えてくれます。でも、自分から探して読むことはありません。本当に、どこで探せばいいのかもわからないんです。Twitterの使い方もわかりません。
――となると、映画批評サイトのRotten Tomatoes(ロッテントマト)もたぶん見たくないですよね?
見たくないです(笑)。必要なことだけ知るようにしています。でも、公開後にあれこれ分析しても、それが自分や作品のためになるとは思いません。
――あなたはこれまで、共演者の演技方法から影響を受けることがあると話しています。今回、義母のパムを演じたシシー・スペイセクと共演したことで、どんなことを得られたと感じましたか?

彼女は本当に“その瞬間”に生きている人なんです。それが意図的なものなのか、彼女の演技プロセスの一部なのかはわかりません。でも、彼女は完全にパムという人物そのものでした。だから、カメラが回っている時と回っていない時の差がほとんどないんです。それは彼女自身の温かさや知性、母性的なエネルギーがそのままパムに生きていたからだと思います。彼女と役が自然に溶け合っていて、撮影前後の移行が本当に滑らかでした。
私は十代の頃に一度彼女と会ったことがあって、さらに彼女の夫(ジャック・フィスク)とも一緒に仕事をしたことがありました。彼は、世界で最も優れたプロダクションデザイナーのひとりです。デヴィッド・リンチ作品を手がけていた人ですよ!
私は彼女のことをずっと前から知っていて、いつもとても優しく、まるで母親のように接してくれました。さらに当時の私は妊娠していたので、彼女は撮影中、とても愛情深く接してくれました。その感じが、そのまま作品にも反映されていると思います。脚本上では、もっと典型的な“義母と嫁”という関係ではあるんですけどね。
▼現代の映画業界へ抱く希望と不安
■観客と時間を共有することの力
――企画を開発したりプロデュースにも関わっている立場として、厳しい状況の中で業界に希望を感じる部分はありますか?
本物のアーティストは、誰にも代わることができない存在です。それは絶対に変わらないので、私は心配していません。
――では、逆に一番不安に感じていることは?
気候変動です。
――映画業界の話で……
ああ。(笑)業界で不安に感じていることですね?映画館での鑑賞について、不安があります。人ってどうしても「楽な方」に流れてしまいますよね。ストリーミングは本当に手軽ですし、私もよく利用します。でも、映画館で大勢と一緒に作品を観るあの経験は、決して置き換えられないものです。たとえば『ワン・バトル・アフター・アナザー』を劇場で観たとき、みんなが同じ瞬間に息をのんだり笑ったりします。そして、上映後に一緒に外へ出ていくあの感覚。まさに“つながり”ですよね。
それに、映画館では作品に集中せざるを得ません。家で観ると、ついスマホを触ってしまう。でも劇場ではそれができないですよね。だから私は、人々が劇場体験を「面倒」と思うようになってしまわないかが不安です。
■今後のキャリアとシリーズ作品への向き合い方
――今後、またシリーズものに出演する可能性はありますか?
シリーズ作品は大好きです。なぜなら、同じ仲間と何年も続けて仕事ができるなんて、めったにないことだからです。本当にすばらしい経験です。なので、「2度とやらない」とは言いたくありません。ただ、幼い子どもが2人いるので、今はなかなかイメージできません。もっとスケジュールに自由がほしいです。でも、“絶対にない”とは言いませんよ。
**
映画『Die My Love(原題)』は、2025年11月7日より全米公開。
※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。編集/和田 萌

【関連記事】
- 『Die, My Love』予告編解禁、愛が壊れるとき、目覚める力
- ジェニファー・ローレンス、トランプ政権を語る「もう発言すべきかわからない」――政治との距離を見つめ直す
- 【第98回アカデミー賞(2026)予想】『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最有力?専門家の最新予測は
- アカデミー賞を受賞したミュージカル映画10本…オードリー・ヘップバーン主演のあの作品も!
- 最も多くのアカデミー賞を受賞したジャンルは?受賞作品を分析