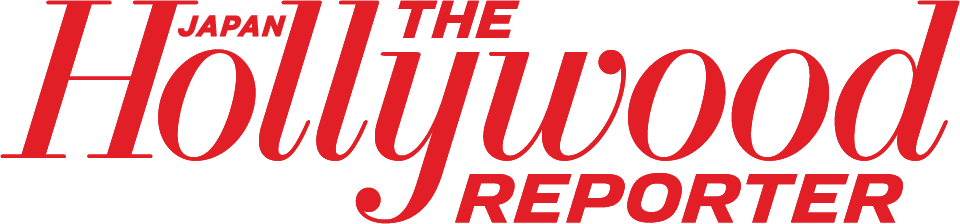世界を揺るがした2025年「ハリウッド事件簿」総まとめ――有名スターの炎上から企業買収、大コケ映画まで徹底解説

炎上・買収・大コケ……2025年ハリウッドの事件簿まとめ
今年もこの季節がやってきた。ハリウッドを中心に、世界を揺るがした2025年の事件簿をまとめて振り返る、年末恒例の特集である。
2025年に勢いを見せた企業や人物、トレンド、そして思うように結果を残せなかった作品まで幅広く取り上げていく。エッグノッグを片手に、気楽に楽しんでもらえたらうれしい。
1. Netflix

配信業界のトップを走る存在は、今年も安定した強さを見せた。世界の有料会員数は約3億人に達し、売上も前年比で約16%増と好調を維持している。さらに、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの一部事業資産取得で合意したことも、大きな話題となった。
作品面でも充実ぶりが際立っている。『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』や『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終シーズンは大きな注目を集め、リミテッドシリーズ『アドレセンス』はエミー賞で高い評価を受けた。『アドレセンス』が英国制作である点は事実だが、高額な予算を投じた続編制作や、シリーズ作品の方向性に悩むよりも、完成度の高い作品を見極めて買い付けた判断は、Netflixの柔軟さと先見性を示していると言えるだろう。
- Netflixのワーナー買収が示すもの ─ AI時代の勢力図はこう変わる
- Netflixがワーナー買収、創業者の孫が複雑な心境を明かす「映画館での上映を守らなければならない」
- トランプ大統領、Netflixによるワーナー・ブラザース買収案に言及「問題になり得る」と警戒感も
2. パラマウント

今年のパラマウントにとっては、どこから振り返ればいいのか迷うほど、厳しい一年だった。旧経営陣のもとで企画された映画の多くが期待に届かず、比較的健闘した例として挙げられるのは『リグレティング・ユー』だった。
人員削減が続くなかで、12作連続ヒットという実績を持つテイラー・シェリダンが離れたことも、大きな痛手となった。
一方で明るい話題もある。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のクリエイターであるダファー兄弟と契約を結ぶことには成功した(本格的な始動は2026年4月以降)。さらに、新体制のもとで、ジョン・M・チュウやジェームズ・マンゴールドといった実力派の映画監督を迎え入れている。
- ワーナー、パラマウントによる16.7兆円の敵対的買収案を拒否 ―― Netflix合併優先、気になるハリウッド再編の行方は
- パラマウントが仕掛けたサプライズ『ミッション:インポッシブル』最新作をモールス信号で配信!?
3. デヴィッド・ザスラブ

気がつけば負債は総額827億ドル(約13兆円)にも膨らみ、試行錯誤するものの、事態は悪化する一方だ。そこへNetflixが現れ、主要事業(スタジオ/配信関連)の買収を持ちかける。結果として、懐には5億6,700万ドル(約886億円※)の資金を確保する形となった。
これほど豪快な“失敗の成功化”は、日々働く大多数の人間にとっては夢物語である。だが、現実にそれを体現しているのがワーナー・ブラザース・ディスカバリーの“再編”である。デヴィッド・ザスラフによる大胆な切り捨てと再構築は、とりわけコスト削減と統合の面で、少なくともウォール街には好意的に受け止められている。
4. ブレイク・ライヴリーとジャスティン・バルドーニ

ブレイク・ライヴリーとジャスティン・バルドーニは、確かに話題性はあった。しかしその一方で、いまなお抜け出せない潰し合いの状態に陥っている。社会的にも法的にも、事態は長期化し、関係者全体の評価に影を落とす結果となっている。この争いに巻き込まれた人たちの多くは、何も得られず、むしろ評価を落とした。
その深刻さを物語る象徴的な出来事もある。『ふたりで終わらせる/IT ENDS WITH US』(2024年)の作者コリーン・フーヴァーは最近、「この本を書いたと言うのは恥ずかしい」と語った。
5. マイケル・デ・ルカとパメラ・アブディ

周囲のだれもが「次は解任だ」と見ていたその直後に、『マインクラフト/ザ・ムービー』『罪人たち』『WEAPONS/ウェポンズ』が相次いでヒットした。その結果、今年はスタジオ作品9本が、世界興収ランキングで初登場1位を獲得するという快挙を成し遂げている。
この成功によって、ワーナー・ブラザースの映画部門トップに対する評価は一変した。業界関係者の視線も厳しいものから称賛へと変わり、解任がささやかれていた空気は一気に消え去った。まさに、見事な逆転劇だったと言えるだろう。
6. ライアン・クーグラーとザック・クレッガー

ライアン・クーグラーによる吸血鬼ジャンルへの大胆かつ痛快なアプローチは、既存のストーリーに依存しないオリジナル作品でも、十分に大きな衝撃を生み出せることを、『罪人たち』で証明してみせた。同時に、クーグラーが唯一無二の才能を持つ映画作家であるという事実を、改めて業界に刻み込んだのである。
そして、『罪人たち』が単なる興行的な一発屋ではないか、という疑念が浮かぶ間もなく登場したのが、ザック・クレッガーによる『WEAPONS/ウェポンズ』だ。知的で構築力に富み、予測不能な展開を備えたこの作品は、オリジナル映画の勢いが偶然ではないことを、はっきりと裏付ける一作となった。
- 映画『Sinners』邦題が『罪人たち』に決定!6月20日より日本公開、空前のオープニング記録を樹立
- マイケル・B・ジョーダン主演『罪人たち』が大当たりした5つの理由
- マイケル・B・ジョーダン、『罪人たち』での熱演が評価されパームスプリングス映画祭で栄誉
7. スター・トレック

このSFフランチャイズは誕生からおよそ60年近くが経ち、その古さを痛感させる局面が続いている。Paramount+で配信された『スター・トレック:セクション31』は失速し、Rotten Tomatoesの観客スコアは16%という厳しい数字を記録した。
『スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド』のシーズン3も評価は芳しくなく、過去シーズンから大きく数字を落とし、観客スコア53%にとどまっている。今後予定されているZ世代向け新作『スター・トレック:スターフリート・アカデミー』に本気で期待しているように見えるのは、レギュラー出演予定のポール・ジアマッティくらいだろう。あるYouTubeユーザーは、予告編を「TikTok版・宇宙プロム」と評していた。
- 『スター・トレック』新作映画をパラマウントが制作へ|監督&脚本が発表!
- 夢と恋に揺れるZ世代『スター・トレック:スター・フリート・アカデミー』が描く、新たな宇宙の物語とは?
- ポール・ジアマッティ、『スター・トレック:スターフリート・アカデミー(原題)』に出演決定
8. テイラー・シェリダン

『殺す前に一つだけ言わせてくれ。あの小さなブラに収まった胸、最高だ』――これは、『ランドマン』に登場するセリフの一例である。こうした作風で知られるにもかかわらず、メガプロデューサーのテイラー・シェリダンは、パラマウントからユニバーサルへと移籍し、最大で10億ドル(約1,560億円※)規模に達する可能性のある大型契約を手にした。
いまやシェリダンは、オフィスに通う必要すらない。牧場から一歩も出ずに仕事を続けることもできる。作品が賞を取るか、批評家にどう評価されるかは、もはや決定的な要素ではない。ハリウッドでこれほど恵まれた立場にいる人物も珍しいだろう。ただし、それは彼に実力がないということを意味するわけではない。
9. アワード番組

長年にわたる視聴者離れを経て、主要アワード番組がついに視聴率の下落トレンドに歯止めをかけ、全体として回復基調に転じた。
エミー賞は4年ぶりの高視聴率を記録し、アカデミー賞は5年ぶりの高水準、トニー賞にいたっては6年ぶりのピークに到達している。
ゴールデングローブ賞は横ばいにとどまったものの、制作側は極めて貴重な“資産”を掘り当てた。広く好意的な評価を得て、少なくとももう1年は続投する意思を示している司会者、ニッキー・グレイザーの存在である。
- 【全ノミネート一覧】第83回ゴールデングローブ賞(2026):『ワン・バトル・アフター・アナザー』最多9部門候補に ――『鬼滅の刃』もノミネート、気になる今年の傾向とは…?
- 【第98回アカデミー賞】3部門のノミネート候補が発表|日本からは『国宝』『鬼滅の刃』などが候補に
- 第77回エミー賞(2025)受賞結果|『ザ・ピット』がドラマシリーズ部門作品賞
10. シドニー・スウィーニー

シドニー・スウィーニーのアメリカン・イーグルの広告に対する反発は、正直なところ行き過ぎた面もあった。しかし、TikTokを中心に何カ月も「人種差別的だ」と批判され続ける状況は、たとえ映画のプレミアで常に注目を集めていたとしても、決して好ましいものではない。
さらに今年は、その空気に重なるように、主演映画3本が興行面で苦戦した。『アメリカーナ(原題)』『エコー・バレー』『クリスティ(原題)』はいずれも低予算のインディー作品で、もともと大ヒットを狙った企画ではなかったが、それでも一部のネット上では失敗を喜ぶ声が目立ったのも事実だ。
一方で明るい話題もある。『ハウスメイド(原題:The Housemaid)』は、堅実なスタートを切りそうな気配を見せている。スウィーニーがスターであることは疑いようがない。ただ、どんな俳優にも、流れに恵まれない年はある。2025年は、彼女にとってそうした一年だったと言えるだろう。
- シドニー・スウィーニー、「ジーンズ炎上騒動」を振り返る──「ヘイトや分断は支持しない」
- シドニー・スウィーニー、子役時代とブレイク、そしてアカデミー賞候補へ――『クリスティ』への思いとキャリアを振り返る
- 【言葉遊びが波紋】アメリカンイーグル×シドニー・スウィーニー広告に賛否、論争の背景を解説
11. Apple TV

『セヴェランス』シーズン2と『ザ・モーニング・ショー』シーズン4がそろって話題を呼び、久々に“人々が本気で楽しみにしている作品”を複数抱える年となった。
だが、真のハイライトは別にある。それが、近年でも屈指の独創性を誇るエイリアン侵略ドラマであり、Apple史上最大のヒット作となった『プルリブス』だ。どんなものでも手に入れられるのに、それでも延々と不満を言い続ける――という設定は、あまりに現代的で、どこかイーロン・マスクを連想させるのは、皮肉が効いている。
- 米批評家が選ぶ!2025年ベスト海外ドラマ&アニメベスト10|『キャシアン・アンドー』『プルリブス』『アドレセンス』…話題作が目白押し
- 『ザ・モーニング・ショー』シーズン4にジェレミー・アイアンズが出演決定
- ジョン・ハム、『ザ・モーニング・ショー』でのジェニファー・アニストンとの関係は「まだ終わっていない」
12. グレン・パウエルとジャレッド・レト

昨年は、『トップガン マーヴェリック』で一躍スターとなった笑顔の好青年、グレン・パウエルの出演作が立て続けに公開されたことから、「グレン・パウエルの夏」とまで呼ばれた。だが今年はというと……言いにくいが、“落ち込みの年”だった。
単独主演のアクションスターとしての実力を証明するはずだった『ランニング・マン』は、期待に届かず、テレビシリーズ『チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦』も、『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』ではないが、同じように人気が出るかもしれないという狙いは空振りに終わった。いずれも、結果は期待外れに終わった。
一方、ジャレッド・レトについては、『トロン:アレス』が失敗に終わった理由は数多く考えられるだろう。だが、業界内外で珍しく意見が一致していた理由があるとすれば――それはジャレッド・レトの起用だった、という点である。ここまで共通認識が形成されるのも、ある意味では稀有だと言えるだろう。
13. ジェームズ・ガン

『スーパーマン』は、興行的には必要な仕事はきっちり果たした。ただし、それ以上でも以下でもない成績だった。それでもなお、ガン監督版『スーパーマン』は、マーベルの3作品『サンダーボルツ*』『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』を上回ってみせた。
テレビ部門でも勝ちは続く。ジェームズ・ガンが手がける『ピースメイカー』シーズン2は、少なくとも最終話までは、近年のディズニープラスによるマーベル作品群より出来が良いと評価された。総合的に見て、2025年は間違いなくガン監督の勝利の年だった(ザック・スナイダーのファンには気の毒だが)。
そして現在、DCスタジオ共同代表としてのガン監督は、破格の報酬を得ながら、やりたいことをそのままやっている。夢見てきたコミック原作を映画化し、気心の知れた仲間をキャスティングする――それが彼の仕事だ。2026年夏公開予定の『スーパーガール』にも期待したい。
- ジェームズ・ガン監督『スーパーマン』デジタル配信開始!新章DCユニバースと公式グッズ紹介
- DC映画・ドラマおすすめ10選|新作『スーパーマン』公開で振り返る必見作
- 『ファンタスティック・フォー』歴代映画まとめ|2025年MCU新作と原作コミック&グッズ完全ガイド
14. スティーヴン・キング原作の映像化作品

愛され続けてきたホラー作家の名作群が、かつてないクオリティで映像化される年になるはずだった。しかし、現実は厳しかった。『ライフ・オブ・チャック(原題)』『The Long Walk(原題)』『ランニング・マン』はいずれも、興行面では期待を下回る結果に終わっている。
もどかしいのは、これらの作品が決して出来の悪い映画ではなかった点だ。とりわけ『The Long Walk(原題)』は、完成度という点でかなりの出来だった。それでも数字がついてこなかった事実は、原作人気と映画の成功がかならずしも直結しないことを、改めて突きつけている。
救いがあるとすれば、HBOによる『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』が、少なくとも評価面では比較的好意的に受け止められたことだろう。現在、ファンはあの“殺人ピエロ”がシーズン更新を勝ち取れるかどうかを固唾をのんで見守っている。
一方、原作者本人であるスティーヴン・キングについては、77歳となったいま、健康面での不調が伝えられている。回復を願わずにはいられない。これ以上キングの小説や短編が読めなくなる世界は、文化的にも感情的にも、あまりに大きな損失だからである。
- 『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー』製作者のムスキエティ姉弟が語るスティーヴン・キングとの制作秘話「原作の余白を埋める物語を」
- スティーヴン・キング厳選!史上最高の映画10本&自作原作映画ベスト4
- 【米レビュー】スティーヴン・キング原作『死のロングウォーク』評価まとめ|フランシス・ローレンス監督×若手俳優が“オスカー級”と絶賛
15. サウスパーク

『サウスパーク』は、最近やや政治色が強くなりすぎているのではないか――そう感じる人がいても不思議ではない。数年後に再放送を見たとき、ピート・ヘグセスやクリスティ・ノームといった当時の政権関係者の名前を、どれほどの人が覚えているのか、という疑問は確かに残る。
それでも、第27シーズンが数十年ぶりの高視聴者数を記録したのは事実だ。その理由はわかりやすい。大統領を正面から、他の番組では到底できないほど過激な言葉で批判する、その大胆さと自由さは、『サウスパーク』ならではのものだからである。ジミー・キンメルがどれだけトランプを批判しても、テレビで大統領をあからさまな罵倒語で呼ぶことはまずない。
さらに追い風となったのが、制作者であるトレイ・パーカーとマット・ストーンが、パラマウント・グローバルと5年総額15億ドル(約 2,338億円※)の大型契約を更新したことだ。その契約内容は、「だれを、どのように笑っても構わない」という自由を保障するものだった。たとえ、その対象が自分たちの親会社であっても例外ではない。
時事性の強い風刺は、いずれ古びてしまうリスクを抱えている。それを承知のうえで、あえていまこの瞬間に踏み込む姿勢こそが、『サウスパーク』がいまも多くの人を引きつけている理由なのだ。
16. 伝記映画

ここ数年、格調高い伝記映画は確実に当たる――そんな空気が確かに存在していた。そこでハリウッドは量産に踏み切った。結果がどうなったかは、言うまでもない。
『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』『クリスティ(原題)』、『ブルー・ムーン(原題)』『The Smashing Machine(原題)』はいずれも、興行面では振るわなかった。題材の知名度や作り手の本気度とは裏腹に、観客の熱は明らかに冷めていたのである。
昨年12月公開の『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は成功例として挙げられるが、ここで一つ冷静に考える必要がある。ボブ・ディランの伝記映画が、ティモシー・シャラメ抜きで、1億4,000万ドル(約218.3億円※)もの興収を上げられただろうか。答えは、おそらく否である。
そして次に控えているのが、ライオンズゲート製作によるマイケル・ジャクソンの伝記映画だ。作品の出来以前に、2026年でもっとも“気まずいプロモーションツアー”になる可能性を秘めた一本として、すでに不穏な注目を集めている。
成功パターンは、繰り返した途端に陳腐化する。伝記映画ブームの失速は、その残酷な現実を、これ以上ないほど明確に示しているのである。
- シドニー・スウィーニー、映画『クリスティ』への想いを語る「この物語は命を救うと信じています」
- ドウェイン・ジョンソン、『The Smashing Machine』の興行不振にコメント「興行成績はコントロールできない」
- ティモシー・シャラメ、初のグラミー賞ノミネート!映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が快挙
17. ユニバーサル

確かにディズニーは、またしても圧勝だった。世界興収は合計60億ドル(約9,354億円※)目前だ。牽引したのは『ズートピア2』『リロ&スティッチ』、そして「最新作なのか? 最終作なのか? とにかく公開した」という形の『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』である。ここまで来ると、もはや驚きはない。
だが、今年称えたいのはユニバーサル・ピクチャーズである。興行面では『ジュラシック・ワールド/復活の大地』『ヒックとドラゴン』『ウィキッド 永遠の約束』が堅実に稼ぎ、存在感を示した。
映画だけではない。テーマパーク事業ではユニバーサル・エピック・ユニバースが予想以上に力強いスタートを切り、苦戦中のシックス・フラッグスにとっては痛手となった。さらに経営面では、NBCユニバーサルのエンターテインメント部門会長であるドナ・ラングレーが、テイラー・シェリダンを引き抜き、ピーコックにテコ入れを図った。
もちろん、失敗がなかったわけではない。『M3GAN/ミーガン 2.0』は、まさかの形で『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』の1週間限定再上映よりも稼げないという屈辱を味わった。それでもなお、ラングレーはこの巨大な船をどう操縦すべきかを熟知していることを、今年も証明してみせた。
- 『ジュラシック・ワールド/復活の大地』完全ガイド:シリーズ最新作&公式グッズまとめ【映画×恐竜×フィギュア】
- 『ヒックとドラゴン』実写公開記念!原作・アパレル・フィギュア徹底紹介
- 『ウィキッド 永遠の約束』公開記念グッズ特集|サウンドトラック、公式アパレルも
- アバター最新作『アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ』公開&グッズ特集 ── 炎の戦いと家族の再起描く新章、2025年12月19日公開
18. 全話一挙配信主義

Netflixは長いあいだ、「新シーズンは全話を同時に配信する」というスタイルを自社の特徴としてきた。少なくとも、そうした方針を掲げてきたと言えるだろう。ところが近年、その例外は少しずつ増え、2025年にはその姿勢に変化が見えてきた。
今年は『ウェンズデー』『コブラ会』『ブリジャートン家』『ストレンジャー・シングス 未知の世界』、さらに『ラブ・イズ・ブラインド』といった人気作が、分割や段階的な配信を採用した。これはNetflix自身が、一度に全話を公開する方法が、かならずしも作品への関心や話題を最大限に高めるとは限らないと認識し始めた結果とも受け取れる。
この考え方は、ハリウッド全体にも共有されつつある。多くの配信サービスが、Netflixの成功モデルを参考にしながらも、いまなお週ごとの配信を続けているのは、話題が時間をかけて広がっていくことの価値を重視しているからだ。作品への関心は、一晩で消費されるよりも、少しずつ積み重なっていくほうが長く続くのである。
実際に、『プルリブス』や『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』は、ゆったりとした展開の中で少しずつ評判を広げ、時間をかけて存在感を高めていった作品の好例と言える。
一方で、Netflixが段階配信の例外を増やしていくほど、従来どおり全話を一度に公開した作品が、十分な準備を経て届けられたものというよりも、まとめて公開された印象を与えてしまう場面も出てきた。かつて「全話一挙配信」を象徴してきた存在だからこそ、そのスタイル自体の価値が、少し揺らいで見えるようになっているのかもしれない。
- ウェンズデー人気再燃!|公式グッズ&歴代『アダムス・ファミリー』作品で世界観を深掘り
- 『ストレンジャー・シングス』知られざるグッズ特集|Netflix公式アイテム・レゴ・キーホルダーまとめ
- ハリウッドが注目!医療ドラマ7選-「希望」と「現実」が交錯する最前線
19. ジミー・キンメルとスティーヴン・コルベア

ドナルド・トランプは、ジミー・キンメルを番組から追い出そうとした。しかし結果は、その思惑とは逆だった。短期間の放送停止を経て、ABCの司会者であるキンメルは、表現の自由を体現する存在として注目を集め、契約の更新にもつながった。
一方、スティーヴン・コルベアが司会を務める『ザ・レイト・ショー』は、5月で終了することが決まった。この判断にトランプがまったく無関係だったとは言い切れず、少なくとも決定のタイミングには影響があったと見る声も多い。ただし、CBSの決断は結果的に、メディアや視聴者の間でコルベアへの支持をこれまで以上に高めることになった。番組は最終的にトーク番組部門でエミー賞を受賞し、長年届かなかった評価を手にしている。
これは、全力で走り切った末の、象徴的な幕引きと言えるだろう。長く続けるには過酷な仕事から、これ以上ない形で去ることになった――コルベアにとって、非常に印象的な締めくくりである。
- 『ジミー・キンメル・ライブ!』の放送停止に各界著名人が反応|司会者のチャーリー・カーク氏殺害を巡る発言が発端
- ABC深夜トーク復活!ジミー・キンメルが語った騒動と全米視聴者の反応
- トランプの圧力逆効果?ジミー・キンメル復帰で視聴率歴代最高を記録
20. 白雪姫

単体の映画をこのリストに入れるのは異例だが、『白雪姫』は観客が露骨に嫌悪する要素を、一本の作品に見事なまでに詰め込んでしまったという点で、象徴的な存在となった。
まず指摘されたのは、原作への配慮が十分に感じられなかったIPの扱い方だ。続いて、主演俳優レイチェル・ゼグラーの発言が一部で波紋を呼んだことも、作品の印象に影響を与えた。加えて、VFXの完成度についても厳しい声が上がり、制作過程では調整を重ねながら進める難しさが見えてしまった。度重なる修正や再撮影も、その印象を強める結果となった。
さらに、家族向け作品でありながら、価値観やメッセージ性が前に出すぎたと感じる観客も少なくなかったようだ。こうした要素が重なり、観客の不満点が一つの作品に集中してしまった点は、やや珍しいケースと言えるだろう。
その結果、『白雪姫』は深刻な不振に終わり、実写版『塔の上のラプンツェル』の企画が数カ月にわたって凍結される事態まで招いた。
- レイチェル・ゼグラー、白雪姫への炎上発言に持論 ファンの情熱
- 実写版『白雪姫』主演のレイチェル・ゼグラー、トランプへの発言について謝罪
- ガル・ガドット、『白雪姫』不振の理由を語る—「政治問題だけが原因ではない」と釈明
21. YouTube

グーグルは、テレビ業界に大きな影響を与え続けている。アカデミー賞は今後、YouTubeでの展開(配信)を強めることになったことも、その動きの一例にすぎない。YouTubeはすでにNFLサンデー・チケットを取り込み、今年は世界最大のポッドキャスト・プラットフォームへと成長した。年間収益は500億ドル(約7.8兆円※)を超え、トム・ブレイディのような著名人までもがYouTubeで発信を始めている。
これは単なる事業拡大ではない。視聴者との接点、配信の仕組み、広告の流れといった、映像ビジネスの要を一社が幅広く握り始めているという点で、業界の構造そのものが変わりつつある。もはや「テレビかネットか」という対立ではなく、ネットがテレビを取り込んだ後の時代に入ったと言えるだろう。
それが不安を感じさせるものなのか、それとも便利で快適なものなのかは、まだわからない。ただ一つ確かなのは、テレビというビジネスがすでに大きな変化の渦中にある、ということだ。
22. 生成AI

これほど多くの反発を受けながら、それでも広がり続ける新技術は、これまでにあっただろうか。AIは、好かれるかどうかに関係なく、着実に前に進んでいる。ディズニーが自社キャラクターをOpenAIにライセンス供与した出来事は、これまで流れを抑えてきた堤防に、大きなひびが入った瞬間だった。
インスタグラムではAIインフルエンサーが高い収益を上げ、ウォール街ではAIを軸にした投資熱が冷める気配を見せていない。その勢いは、エンタメ業界にも静かに浸透している。
ハリウッドではすでに、脚本の分析や絵コンテ作成、編集、VFXの調整といった工程でAIが活用されている。物語の展開やセリフのアイデアが、どこまでAIの助言を受けて生まれているのか――その境界は、もはやはっきりしなくなりつつある。
一方で、言葉の世界はAIに警鐘を鳴らしている。米メリアム=ウェブスター社が今年の言葉に選んだのは「slop(粗悪なもの)」、つまりAIスロップだった。また、マッコーリー辞典が2024年の言葉に選んだ「enshittification(劣化化)」が示すように、AIがデジタル・コンテンツ全体の質を下げているのではないか、という見方も広がっている。
さらに登場したのが、年を取らず、スキャンダルとも無縁なAI俳優、ティリー・ノーウッドだ。現実の俳優たちが脅威を感じるのも無理はない。制作側にとって、これほど扱いやすい存在はないからである。
結局のところ、AIは多くの人が戸惑いを覚えながらも、すでに手放せなくなっている技術だ。拒否と依存が同時に進む――それこそが、2025年におけるAIの現実的な姿だったと言えるだろう。
23. ペドロ・パスカル

2025年は、ペドロ・パスカルの飛躍年だった。『THE LAST OF US』でファンを号泣させ、その直後には『エディントンへようこそ』『The Materialists(原題)』『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』に立て続けに主演級で登場した。もはや“どこにでもいる”状態となり、同時期に同じ映画館のロビーにパスカル主演作のポスターが3枚並ぶ様子を写した投稿が拡散したほどだ。
才能や好感度に疑いはない。しかし、出演があまりにも続くと、観客の受け止め方は、称賛から「少し多すぎる」という感覚に変わりやすい。2025年のパスカルは、そのラインをはっきり越えてしまったように見えた。
アイオウ・エディバリーも同じである。『一流シェフのファミリーレストラン』でエミー賞級の評価を受けつつ、映画『Opus(原題)』『アフター・ザ・ハント』『Ella McCay(原題)』、さらにHBOのコメディシリーズ『I LOVE LA』と出演作が続いた。ただし、出演本数の多さに比べて、強く印象に残るヒットは生まれず、話題性はやや控えめにとどまった。
スターにとって本当に厄介なのは、失敗よりも、成功が続きすぎることだ。2025年は、その現実をはっきりと示した一年だった。
- 『ファンタスティック4』公開直前!ペドロ・パスカルの必見出演作11選を総復習
- 「不快」「天才」の評価続出 アリ・アスター最新作『エディントンへようこそ』で監督が生回答
- ドラマ『THE LAST OF US』シーズン3、まさかの主役変更?製作者が予告【S2ネタバレあり】
※記事内の円表記は、2025年12月26日時点の為替レートで換算
※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。

【関連記事】
- 『ズートピア2』公開記念グッズ特集|あらすじ・声優キャスト・前作の見どころまとめ
- 【映画ファン・プレゼント】非売品『第38回東京国際映画祭特別号』を抽選でプレゼント|ハリウッド・リポーター・ジャパン
- 【2025年ベストアルバム】米・音楽編集者が選ぶ記憶に残る10作|カーター・フェイス、ザラ・ラーソン、ATEEZ、F5veほか
- 【ランキング】米評論家による、ジェームズ・キャメロン監督作品ベスト12|首位に輝いたのはあの名作
- 米批評家が選ぶ!2025年ベスト海外ドラマ&アニメベスト10|『キャシアン・アンドー』『プルリブス』『アドレセンス』…話題作が目白押し