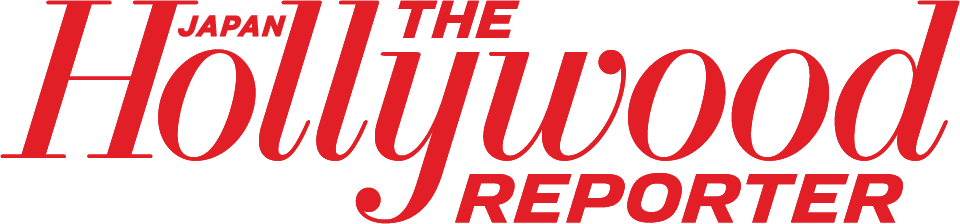日本発コンテンツが今、転機を迎えているワケ ―「日本文化に対する世界の関心は、これまでにないほど高まっている」

Netflixのアジアを拠点とするコンテンツ・エグゼクティブ、キム・ミニョン氏はここ数年、東京で活動し、同プラットフォームにおける日本発作品の基盤を築いてきた。同社は、日本のエンターテインメントが大きな復活を遂げる可能性があると考えているのだ。
昨年は『ゴジラ-1.0』が大ヒット…日本作品に世界が注目
Netflixドラマ『イカゲーム』を手がけたことで知られるキム氏は、「つい最近まで、韓国文化はそれほど注目されていませんでした。しかし、ポップ・エンターテインメントが強みとなり、世界中の人々から興味を引くことができたのです」と語る。「今の日本は、ほぼ真逆の状態です。日本文化に対する世界の関心は、これまでにないほど高まっており、国内のエンタメ業界が勢いを取り戻すポテンシャルは大いにあるでしょう」
日本コンテンツを受容する世界的な動きは、2023年の北米の興行成績にも表れていた。巨匠・宮崎駿によるアニメ映画『君たちはどう生きるか』は昨年12月、興収1280万ドルでデビューを飾り、自身のキャリア史上最高となる北米初週興収を記録。また、同じ週には東宝の『ゴジラ-1.0』が公開2週目で2530万ドルを突破し、北米で公開された日本の実写映画の歴代興収で1位となった。
今の日本が持つ魅力とは?
一方で、キム氏によると、Netflixやその他の主要ストリーミングサービスは、SVOD普及の余地が存分にある日本の大規模な高所得者市場と、世界的に見て長年にわたり十分に活用されてこなかったクリエイティブ産業(特に実写エンターテイメントに関して)に非常に興味を持っているという。
「海外の重要な企業は日本に可能性を感じ、参入しようと試みています。それが過度に大きなバブルを引き起こさない形で行われる限り、日本の業界全体を活性化する非常に健全な刺激になり得ると思います」
膠着状態から脱却なるか
日本のテレビ業界は、20世紀後半の大部分において、アジア地域の創造的・商業的なリーダーだった。特に1970~80年代の日本ドラマは、後に韓国で出現する革新的なテレビドラマ産業のテンプレートの1つとして機能した。しかし、国内のテレビ産業は、バブルが崩壊した90年代から2000年代初期に、かつての勢いや革新的な精神を失い始めた。つまり、ハリウッドが“プレステージTV”(=上質な番組)の黄金時代を迎え、韓国ドラマが成長を続け、やがて世界を席巻する一方で、日本のプロダクション・バリューやストーリーテリングのテンプレートはほとんど膠着状態となったのである。
コンサルタント会社・Media Partners Asia(MPA)の推計によると、日本の定額制動画マーケット全体の年間収益は、現在46億ドル。その一方で、最低1つの定額制動画配信サービス(SVOD)に加入している世帯の割合は、44%にとどまっている(アメリカは86%)。同社は今後5年間で、日本のSVOD全体の収益は毎年約5%ずつ増加していくと予測している。
「SVOD業界において、日本は中国に次ぐシェア」
MPAの共同設立者、ヴィヴェック・クート氏は次のように語っている。「SVOD業界において、日本は中国に次いで最大のシェアとなっています。すでに大きなビジネスで、収益性の高い機会であり続けているのです」
日本のアニメは、しばらくの間ブームが継続している。日本動画協会によれば、日本アニメの世界市場は2021年、13%拡大し、史上最高となる2兆7400億円に達した。また、Netflixは同年、世界中の会員の半数が何らかのアニメコンテンツを視聴したと明らかにした。さらに、アニメカテゴリの作品を視聴した日本の会員は、90%に上るという。
実写作品が顧客獲得のカギに
しかしながら、日本のエンタメ業界では、実写シリーズこそが海外の大手ストリーミング企業からの投資が急増し、プロダクションの基準が最も変化している分野なのだ。業界関係者たちは、実写作品は再活性化をもたらす大改革への可能性を持っていると口をそろえる。
MPAの主任アナリスト、ディヴィヤ・T氏は、「日本のSVODサービス全体を分析すると、アニメは顧客の維持とエンゲージメントに必要不可欠な基本要素となっています。その一方で、顧客獲得に関しては、実写作品が非常に大きな効果をもたらしているのです」と述べた。
『今際の国のアリス』&『ONE PIECE』が大ヒット
Netflixは近年、ドラマ『サンクチュアリ -聖域-』や『First Love 初恋』をはじめ、漫画を映画化した『ゾン100 ゾンビになるまでにしたい100のこと』、『シティーハンター』など日本の実写作品の制作を大幅に増加してきた。
中でも、ドラマ『今際の国のアリス』シーズン2は世界的なヒットを記録し、Netflixで最も視聴された日本のシリーズとなった(アニメ作品を含む)。さらに、日本の有名漫画を映像化したドラマ『ONE PIECE』は、かつて『ストレンジャー・シングス 未知の世界』や『ウェンズデー』が打ち立てた記録を破り、86の国で1位デビューを飾った。
“実写化不可能”とされていた『幽☆遊☆白書』を5年かけて制作
Netflixは昨年末、90年代に出版された同名漫画をドラマ化した『幽☆遊☆白書』と、ストップモーション・アニメシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の2本の日本発作品を配信。同社は、2023年の終わりまでに日本が非英語作品カテゴリーの視聴ランキングで韓国、スペインに次いで3位となると見込んでいた。
特に、『幽☆遊☆白書』は日本の実写作品をレベルアップする機会に対するNetflixの強気な姿勢が表れている。絶大な人気を誇る原作漫画は、驚異的な妖怪のキャラクターや、撮影が困難に思えるアクションシーンが登場することから、“実写化不可能”だと考えられてきた。しかし、Netflixはシーズン1(全5話)の制作に5年を費やし、ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』を手がけたScanline VFXをはじめとする世界中のVFX制作会社8社が、共同で作業した。
昨年12月13日には、東京の有明アリーナで『幽☆遊☆白書』のレッドカーペット・イベントが開催され、5000人以上のファンが駆けつけた。Netflixにとって、アジアのオリジナル作品としては過去最大のプロモーション・イベントで、単一作品としても最大級のプレミアの1つとなった。
Netflixは『幽☆遊☆白書』や『今際の国のアリス』の予算を公表していないが、業界関係者は、この2作品が1話あたりの製作費が最も高額な日本語シリーズだと予測している。一方で、同社は日本への投資がすぐに実を結ぶとは考えていないようだ。
Netflixのコンテンツ・エグゼクティブ、キム氏は語る。「8年前に東京オフィスを開設し、日本はアジアにおいて最も長く事業を展開している国です。とはいえ、最も多くのことを学ぶ必要がある市場であり、学びは今でも続けています。実写作品の戦略という点では、韓国やインドに比べて、まだ新しい段階にあると感じています」
Netflixが世界各国の業界に対して、制作アプローチなどを強制することはない。しかし日本では、ライセンス契約の後でも漫画原作者がIP(知的財産)への厳格な管理権を保持したり、業界において芸能事務所が絶大な力を持っているといった実情がある。それに適応するためにも、Netflixは他国以上に日本のやり方に合わせるほかないのだ。
リアリティ番組の根強い人気
プライム帯のテレビ番組の70%を、リアリティ・バラエティ番組が占める日本。NetflixやPrime Videoなどの米国の配信サービスは、『テラスハウス』、『あいの里』、そして『バチェラー・ジャパン』といった作品で成功しているが、日本のテレビを独占するこれらのカテゴリーを存分に活用できているとは言えない。
キム氏は、「大半の国では、台本のあるシリーズの方がより大きな影響力を有しています。台本なしの作品はある程度必要とされる一方で、主力ではないのです。日本では、Netflix上でも台本なしの作品が台本のある作品と同じくらい影響力を持っています」と見解を示した。昨年8月にソウルで台本なしの作品の紹介イベントが開催された際には、日本のリアリティ番組が15本進行中であることが伝えられた。
国内で有料コンテンツへの需要が増大
2020年に日本で展開されたDisney+は、ドラマ『ガンニバル』やドキュメンタリー映画『Shohei Ohtani – Beyond the Dream』などでヒットを記録。そして今年は、FX製作のドラマ『SHOGUN 将軍』を筆頭に日本作品のラインナップが拡大し、今後2年間で講談社とのパートナーシップにより10本の新作オリジナルアニメが配信される予定だ。また、ワーナー・ディスカバリーが提供するMaxは、『TOKYO VICE』シーズン2を今春にリリースした。
ディズニーのオリジナルコンテンツ担当エグゼクティブディレクター・成田岳氏は、「日本の状況が、すぐに変わるわけではありません。しかし私たちは今、大きな変化の瀬戸際にいます。投資や最善のプロセスが流入するなか、日本人視聴者の間で有料コンテンツに対する需要はますます高まっており、業界に変化を起こす機会を創出しているのです」と述べた。
日本国内のテレビ放送局も、すでに変化に対応し始めている。TBSが主要株主に名を連ねる配信サービス・U-NEXTは、国内外問わず映画・ドラマ、アニメやスポーツなど多岐にわたるコンテンツを提供し、着実に成長を続けている。日本のSVOD業界では、収益においてAmazon、Netflixに次ぐ3番手(下記、チャートを参照)に位置し、今後数年間にわたって自社のオリジナル作品の制作を強化していく予定だ。
日本の映画・テレビ業界の課題とは?
海外・国内からの需要が増大する今、日本のタレントやプロダクション施設がそれに対応していけるかが、業界内で最大の障壁となっている。
Netflixコンテンツ部門バイス・プレジデントの坂本和隆氏は、「日本はキャストやスタッフに同じ人ばかりを起用する傾向があり、撮影スタジオも非常に限られているので、そこは間違いなく困難な問題ですね」と指摘した。
訪れる転機…今後の展望は
Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』や『今際の国のアリス』を手がけたThe Seven(TBSが出資する製作会社)は昨年12月、総工費20億円をかけたスタジオをオープン。慢性的なスタジオ不足を解消しつつ、海外プラットフォームの有料コンテンツに対する需要の高まりに対応していくという。その他の日本の大手ネットワークも、同様のアップグレードを視野に入れていると伝えられている。
The Sevenのチーフコンテンツオフィサー・森井輝氏は、「旧来のシステムから脱し、新たな時代を見据えるプロデューサー、脚本家、監督や俳優が増えてきています」としながら、「次なる黒澤明監督が現れるには、まだ早いでしょう。一方で今の映画・テレビ業界は、クリエイターが自分たちの思い描いた野心的なコンテンツを制作することができると感じられるような段階にあります」と考えを明らかにした。
記事/Patrick Brzeski
翻訳/和田 萌
※初出は米『ハリウッド・リポーター』(2023年12月15日号)。