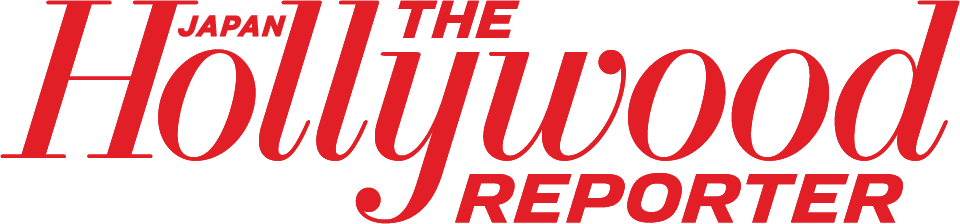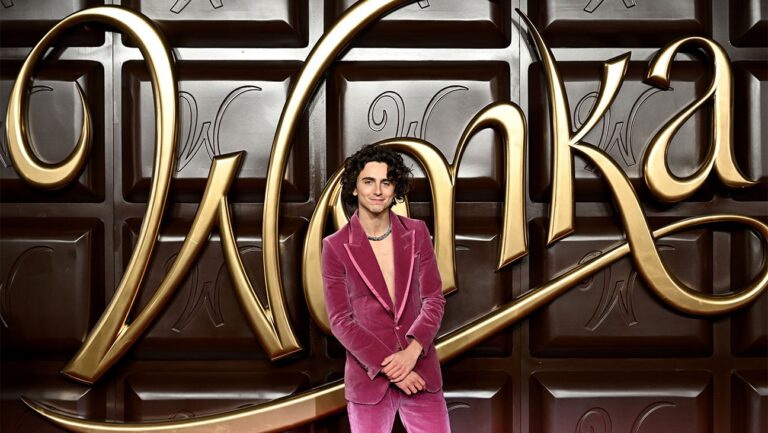映画『遠い山なみの光』がカンヌへ 石川慶監督が語る、原作者カズオ・イシグロとの制作秘話

ノーベル賞作家カズオ・イシグロによる1982年の長編デビュー小説を映画化した『遠い山なみの光』が今年、現在開催中の第78回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で上映される。監督を務めたのは、2022年のヴェネツィア国際映画祭で高い評価を受けた『ある男』の石川慶だ。
『遠い山なみの光』は1982年のイギリスに暮らす日本人女性・悦子が、戦後の長崎での若き日々を回想する形で進行する。彼女は幼い娘を連れてアメリカに移住する夢を抱いていた謎の女性・佐知子との奇妙な友情など、日本で過ごしたかつての人生を語り始める。
しかし、イギリスで生まれ育った次女・ニキが母に質問を投げかけるにつれ、悦子の語る物語の中に矛盾が見え隠れし始める。それらは、長尺のフラッシュバックとして画面に映し出される。「誰が誰の記憶を語っているのか?」、「そして、その記憶は何を隠しているのか?」――観客にそう問いかける構成となっている。
◆制作のきっかけは“ある会話”
「あるプロデューサーから、『カズオ・イシグロの小説を映画化することに興味はあるか』と聞かれたのが始まりでした」と石川監督は回想する。「多くの日本人映画監督と同様に、僕もイシグロ氏に長く敬意を抱いてきました。ただ、それは非常に大きな挑戦で、ゼロからのスタートになることは明らかでした。その時点では、原作の権利すら取得されていなかったんです。すべては情熱だけが頼りでしたね」
石川監督は、日本を舞台にした作品がイシグロの小説の中でこの作品を含めて2つしかなく、まだ映像化されていなかったため『遠い山なみの光』を選んだという。
「NHKが、もう一つの日本を舞台にした作品『浮世の画家』を映像化していました。また、僕たちは黒沢清さんのような他の監督たちも『遠い山なみの光』の映画化を検討したことがあると聞いていました。しかし、何らかの理由で実現には至っておらず、自分たちで挑戦することに決めたのです」
◆イシグロの反応と共同製作
イシグロは、若い世代の日本人映画監督が自身のデビュー作の映像化を試みることを望み続けており、企画を快く引き受けたそうだ。本作のテーマにおいて、世代を超えた歴史の継承は極めて重要な要素となっている。
その後、両者によるコラボレーションのもとで映画化プロジェクトは進行し、イシグロは製作総指揮としても参加。「僕は非常に幸運でしたね」と石川監督は語る。「イシグロ氏は映画『生きる LIVING』(2022)の脚本を仕上げた直後で、映画製作者としての視点を持ってこのプロジェクトに臨んでくれたんです。脚本についても、詳細なフィードバックをもらえました」

脚本の開発過程において、石川監督はロンドンを訪れ、イシグロと長時間にわたる対話を重ねた。「彼は、小説の中でどこが機能していたか、どこがそうではなかったか、そしてどのように進化させるべきかを丁寧に語ってくれました。まるで、“脚本のドクター”と作業しているようでしたね。彼はノーベル賞を受賞した脚本ドクターです」
「イギリスの場面でチェルノブイリ原発事故を示唆する案も考えたのですが、彼は代わりにグリーナム・コモンでの反核運動を提案しました。女性の権利や社会運動との関連を重視した結果であり、それが物語の重要な主題の一つとなったのです」
さらに石川監督は、「イシグロ氏は映画の編集の段階では意見を出さなかった」と明かす。「それは、1本の映画として完成させるには、最終的なビジョンは1人の監督によるものであるべきだ、という考えからでした。また、自分の意見が重く受け取られすぎることを懸念していたようです。しかし彼のその姿勢が、他のプロデューサーたちにも影響を与え、僕のビジョンが尊重されるべきだという空気を作ってくれたのです。創作過程で困難を感じていた僕にとって、大きな支えとなりました」
◆「描かれないこと」に宿る力
石川監督の演出は、語られないものにこそ力が宿るという信念に基づいている。50年代の長崎を描いた場面には、戦争の余波とトラウマが静かに漂っているが、原爆投下そのものは直接的に描かれない。
「多くの日本人監督にとって、いつかはその歴史的遺産と向き合わねばならない瞬間が訪れます。それは簡単なことではありません。僕たちはすでに何世代もその出来事から離れており、直接の記憶を持つ人々も少なくなっています。しかし、それでも僕らはその過去を受け継いでいるのです。イシグロ氏が用いる“不確かな語り手”という手法は、単なる文学的技法ではなく、記憶と歴史の曖昧さを認め、それと向き合うための手段となっています」
『遠い山なみの光』は、歴史を個人的な神話として描いている。断片化された記憶が物語を形成し、その語り口は感動的であると同時に、深い曖昧さを内包している。
「映画の中で、娘が『あなたとあなたの時代のこと、全部を理解しているわけじゃないと思う』と語る場面があります。この感覚こそ、僕が観客に味わってほしかったものです。過去を完全に理解することはできなくても、その本質的な何かを受け継ぐことは可能だと思っています」
◆映像と音楽による時代の再構築
本作の撮影監督を務めたのは、ポーランド出身のピオトル・ニエミイスキ。絵画的な映像を通して、イシグロ自身も影響を受けた小津安二郎や成瀬巳喜男といった戦後日本映画の巨匠たちの美学を意図的に喚起するものとなっている。
音楽は同じくポーランドの作曲家パヴェウ・ムウィキェティンが手がけた。石川監督はポーランドの国立映画大学で映画製作を学んでおり、本作は同国のインディーズ制作会社Lava Filmsとの共同製作となっている。
石川監督は、原作小説から2つの重要な改変を加えている。1つは物語の視点を80年代のイギリスに暮らすニキに移したこと、そして映画の冒頭とラストに、イギリスのバンドであるニュー・オーダーのデビューシングル「Ceremony」(1981)を使用したことだ。
「このような音楽を日本映画で使うのは珍しいですが、あえて挑戦したかったんです。80年代は音楽の黄金期でした。『Ceremony』は死や喪失という主題に触れていて、曲のムードもタイトル自体も、作品にぴったりです」
◆理想的なキャスト陣
石川監督が、「夢のようなキャスティング」と語るキャスト陣も本作の魅力の1つだ。若き悦子役には、カンヌ常連の広瀬すず(『海街diary』)が起用され、繊細で儚い存在感を発揮。一方、80年代の悦子には吉田羊が扮し、深い含みをもった演技で物語を支える。
また、佐知子役の二階堂ふみは鋭い魅力を放ち、悦子の父親を演じる三浦友和は戦後の変化についていけず葛藤する父親像を、静かで圧倒的な演技力で体現している。
「彼はまさに“イシグロ的キャラクター”です」と、石川監督は三浦演じる父親について語る。「一部の人々は、物語の主軸に直接関わらないこの人物をカットしてはどうかと提案してきましたが、僕はそうしたくなかったんです」
イシグロ自身も、「『遠い山なみの光』では父親像を十分に描けなかったので、『日の名残り』に引き継いだ」と語ったことがあるという。石川監督はその発想に深く惹かれたといい、「1人の登場人物が作品を越えて生き続けるという考え方に魅了されました。問題を抱える過去を持ちながらも、父親はどこか深く共感を呼ぶ存在であり、彼のことをずっと考えずにはいられませんでした。――それが、イシグロ氏の魔法なのです」
本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。編集/和田 萌
【関連記事】
- 広瀬すず、10年ぶりカンヌで主演の『遠い山なみの光』お披露目「映画が届いたと実感」
- 映画『恋愛裁判』が描く日本のアイドル業界の闇:今年のカンヌに出品、大注目の衝撃作
- 【カンヌ国際映画祭2025】日本人監督の過去作品をご紹介!早川千絵監督『PLAN 75』ほか
- 【カンヌ映画祭2025の必見作10本】鬼才アリ・アスターの異色作、ジェニファー・ローレンス主演最新作も!
- 『ウィキッド』DVD・ブルーレイ:特典付き限定セット予約開始!
- 【11作品厳選】プライムビデオで話題の新作映画を今すぐ視聴