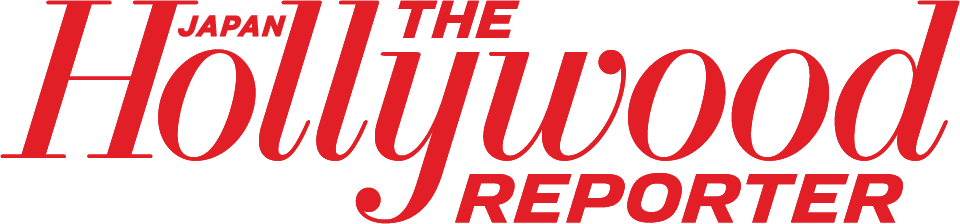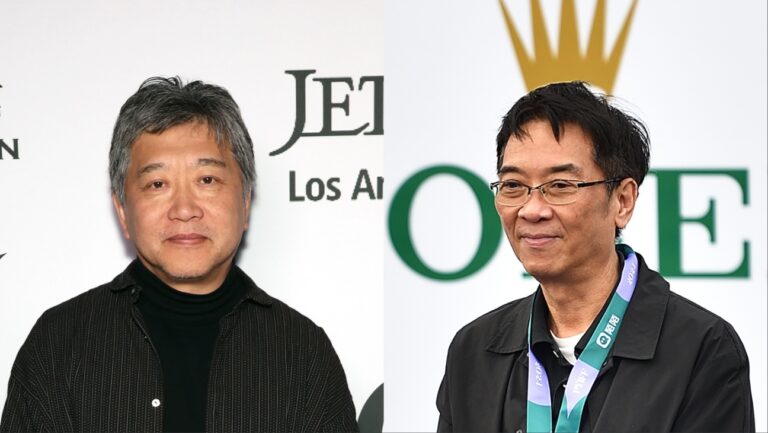「映画ジャーナリズムにおける女性のまなざし」について各国の記者、評論家が活発な議論

第36回東京国際映画祭で26日、「映画ジャーナリズムにおける女性のまなざし」と題したシンポジウムが行われた。参加メンバーは、映画祭ナビゲーターの安藤桃子監督がモデレーターを務め、読売新聞編集委員の恩田泰子氏、映画評論家でシリアとフランスの二重国籍を持つナダ・アズハリ・ギロン氏、英国のウェンディ・アイド氏、香港のセシリア・ウォン氏の5人。

いずれも20年以上のキャリアを持つベテランで、恩田氏は女性記者の人数の変遷について「会社の中での割合としては少しずつ増えている。私が海外の映画祭に行き始めた2000年代初めは、フリーランスの方はほとんど女性でいろいろと教えてもらった。ただ今は、書く場所がネットなどで広がって、どの記者の記事がどこでアクセスすれば読めるのか見えにくくなっている」と分析。オブザーバー紙などで執筆しているアイド氏も、「記者の数は増えているが、プロフェッショナルとして収入を得ている人は少ない。多くはフリーで、確立された企業でチーフ・エディターをしている女性は私だけ」と見解を示した。
ウォン氏が「ジャーナリストと評論家の境界線なくなってきている」と話すと、安藤監督が「その違いで、これだと思うものは」と質問。アイド氏が「評論家はレビューを書く人で、ジャーナリストはそれに加えインタビューや特集記事を書く人。評論家はスターや監督とはある一定の距離をとらなくてはいけない」と説明すると、ギロン氏が同意。双方をこなしている恩田氏は、「批評を書く際は、インタビューなどで聞いた余談が入らないように注意している」と明かした。
安藤監督が、2000~22年に日本で興行収入10億円以上の作品796本のうち女性監督の作品25本、わずか3.1%というデータを基に女性監督の少ない現実を踏まえた上で、男性と女性で映画を見る視点の違いに言及。アイド氏は「男性が描く女性の表情などに違和感を覚えることはある。どこか理想を重ねている場合が多い。例えばウディ・アレンの映画」と指摘。ギロン氏は、「アラビア圏の映画では、女性が被害者として描かれることが多い。これを変えていかなければいけないと思っている」と言葉に力を込めた。

恩田氏は、「女性だからこういう見方をしようというよりも、人間として見ようとしている。ただ最近は、映画の中に女性の視点を感じるものが増えて、その置かれた状況を理解できるから書くべきと思える作品も増えた」と持論。キティ・グリーン監督の「アシスタント」(2019)、アリス・ディオップ監督の「サントメール ある被告」(2023)を例として挙げた。
ジャーナリズム界における女性の地位向上のためには、全員が「まじめに取り組み仕事で証明していくしかない」という意見で一致。安藤監督は、「今も時代の変化の真っただ中にあるのだから、男性、女性ではなく人類全体で一体感を持ってやっていきたい。映画は世界の共通言語。優しい心で未来に進んでいきましょう」と呼びかけた。
取材/記事:The Hollywood Reporter 特派員 鈴⽊ 元