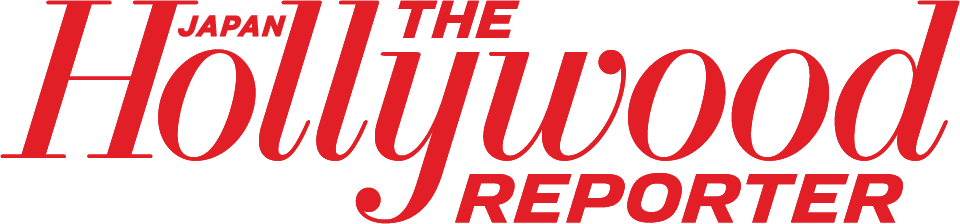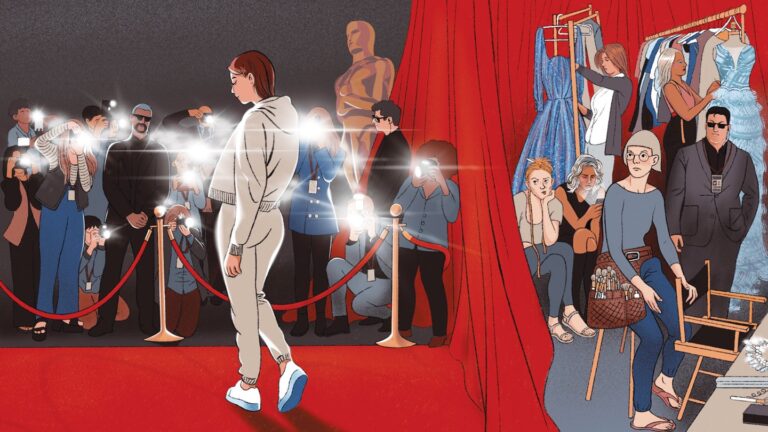映画『ザ・ウォッチャーズ』ネタバレ考察:裏側に隠された意味とは?

[本記事は、映画『ザ・ウォッチャーズ』のネタバレを含みます。]
M・ナイト・シャマラン監督の娘である24歳のイシャナ・ナイト・シャマランの長編デビュー作『ザ・ウォッチャーズ』(公開中)。
A・M・シャインによる小説を原作とする『ザ・ウォッチャーズ』は、アイルランドの森で車が故障し、森に迷い込んだ若きアーティスト・ミナ(ダコタ・ファニング)の姿を描いたホラー作品だ。
『ザ・ウォッチャーズ』あらすじ
ミナは、森の中でマデリン(オルウェン・フエレ)にガラス張りの小屋「ザ・クープ」へと案内され、素朴で楽観的なキアラ(ジョージナ・キャンベル)と、情緒不安定で謎めいたダニエル(オリバー・フィネガン)に出会う。
4人は夜になると「ザ・クープ」に滞在し、小屋の外にいる「監視者」が彼らを研究している間、鏡に映る自分の姿を見つめ返す。ミナたちは、“日没までに小屋に戻り、監視者が住む穴に近づかない”というルールのもと、日中は森の中を自由に動き回ることができる。
このような監視されていない瞬間にこそ、登場人物たちは最も人間らしい自分でいることが許される。しかし、夜のミナたちのパフォーマンスには、『ザ・ウォッチャーズ』をよりユニークな作品にしている隠れた意味合いがある。

監視と行動
人間は、異なる集団の中で言葉遣いや振る舞いを変える「コード・スイッチング」を行う。これは一種のパフォーマンスであり、私たちが観察され、判断され、行動に対して非難されたりしていることを認識している表れだ。また、自己防衛のための行為でもあり、通常は人種と文化の両方に根ざしている。
「監視者」が、小屋の4人とは人種や文化、そして種さえも違うことは、早い段階で明らかになっている。そのため、ミナたちは監視されているときの行動を変え、より慎重な行動を取るようになる。
また、彼らはすぐに一種の序列に陥り、マデリンが保護者、他の3人は子供や兄弟姉妹のような立場に置かれる。しかし、映画とは画面上に登場する人物だけでなく、その背後にいる人々についても語るものだ。
映画監督の父を持つイシャナ
イシャナ監督の父、M・ナイト・シャマランはインドに生まれ、生後6週間で米ペンシルベニアに移住。M・ナイト・シャマランは2000年、カトリックの学校で部外者のように感じていたと、子ども時代の経験について語った。
ハリウッドで「次なる大物」と呼ばれるインド系アメリカ人の若手映画監督として、期待に応えなければならないというプレッシャーがあったに違いない。
『ザ・ウォッチャーズ』が描く内容からすると、父のキャリアの浮き沈みを目の当たりにしてきたイシャナは、「監視される」とはどういうことなのか、その全容を考えているような気がする。それは、登場人物たちの扱い方や、枠にはめられ、晒され、物語を裁かれることに対する彼らの感受性に表れている。
ミナと鳥のメタファー
ミナは序盤、ペットショップで働いていた。15年前に母親を亡くした彼女は自分を責め、双子の姉がいるアメリカを去り、アイルランドへと移住。店内のテレビでは、生息地が破壊され、地元の動植物が逃げ出さざるを得なくなったというニュースを放映され、森林伐採や気候変動に関する新聞の見出しも垣間見える。
ミナもまた、過去から逃避するあまり、自然の秩序が乱れ、追い出されてしまったのだ。彼女はウィッグやコスチュームを身につけて、パブに出向いたりすることで、自分ではない誰かに見られようとしたり、馴染もうとしたりする。
そして、世話をしているペットショップの鳥・ダーウィンのように、ミナも自分の境遇に縛られ、飛ぶことができないのだ。
「監視者」の正体は?
では、森にいる謎めいた「監視者」とは何者なのか?『ザ・ウォッチャーズ』は単なるホラー映画ではなく、現代の寓話であり、おとぎ話なのだ。「監視者」は、妖精あるいはチェンジリングと呼ばれるアイルランド民話に登場する生き物で、人間の姿に変身することができる。
かつて彼らは人間と共生し、神として崇拝され、人間と結婚し、ハーフリングという子孫を残した。その後、妖精たちの変身能力やハーフリングの力を恐れた人類は、彼らを地下深くに閉じ込めた。妖精は何世紀もかけて地表に這い上がり、翼を脱ぎ捨て、「監視者」(ウォッチャーズ)として現れた。人間の中で暮らすことには満足せず、人間を研究し、取って代わろうとしたのだ。
この側面は、一部の人々には見落とされているようだが、『ザ・ウォッチャーズ』を十分に理解し、本作が提示する視点を捉えるために不可欠な要素となっている。
作品の3つのテーマ
このおとぎ話の中では、植民地主義、混血、盗用という3つの事柄が扱われている。これらの側面は、ヨーロッパによるインドの侵略、英語圏におけるインド人の移民と同化、そして工芸品や文化の盗用をもたらした「オリエンタリズム」とも明確なつながりがある。
人間は常に自分たちとは異なる人間に魅了され、彼らが持つものを欲しがり、そして異人種間の交配が自分たちの存在を侵食する可能性を恐れるようになる。その結果、故郷は破壊され、有害物質は大気を汚染し、先住民はより小さな空間、つまり「小屋」(ザ・クープ)に閉じ込められる。
これは世界の歴史であり、ホラーやファンタジーの形態をとることで消化しやすくなり、若い白人女性の目を通して見ることで受け入れやすくなるのだろう。『ザ・ウォッチャーズ』は、イシャナ監督が父親の作品や文化の歴史などに影響を受けながら、自身が育ってきた世界を見つめる意図的な試みのように感じられる。
ミナとイシャナ監督の共通点
『ザ・ウォッチャーズ』のテーマは、模倣と置き換えに重点を置いている。パフォーマンスの観察と研究は、単なる再現だけでなく、元の対象よりも優れたものを作り出すための賭けとも言える。ミナは双子であり、変装を通じて自分の分身を作り出す人物だが、同時に彼女に取って代わろうとするチェンジリングにも翻弄されてしまう。
このチェンジリングの正体(ここでは明かさない)は、学問の名の下に行われる文化の盗用、恐怖、そして貪欲さという観点からも、さらなる複雑さを加えている。ミナが自分の檻から逃れ、独自のアイデンティティを形成する唯一の方法は、過去を受け入れ、家族の歴史と未来とつながることなのだ。
イシャナ・ナイト・シャマランは、父親の物語作りの信条をいくつか受け入れているが、単なる模倣以上の存在であると主張している。イシャナ監督の芸術性は、その名前が持つ重みに関係なく、彼女自身を基準にして定義されるべきなのだ。そうすることで、彼女の経験や歴史的知識が、このおとぎ話の慎重な楽観主義をどのように形作ったかを考察することができる。
本作は最終的にミナを自由にするが、それでも彼女は観察され、判断される。こうして、イシャナ監督は私たちに監視を続けるよう促し、彼女の思いと視点がキャリアを通じてどのように発展していくかを目撃するように誘っているのだ。
※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。翻訳/和田 萌
【関連記事】
- M・ナイト・シャマラン監督最新作『Trap』予告解禁 8月9日全米公開 – THR Japan (hollywoodreporter.jp)
- 【ネタバレ】『猿の惑星/キングダム』ノヴァは何者?続編の可能性も? ― フレイヤ・アーランが回答 – THR Japan (hollywoodreporter.jp)
- ザック・スナイダーが『REBEL MOON パート2』をネタバレ解説、続編の可能性も…? – THR Japan (hollywoodreporter.jp)