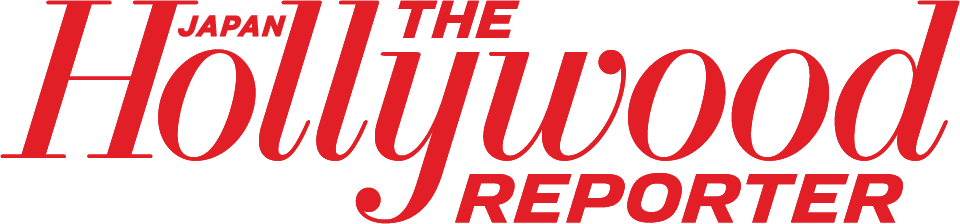エド・シーラン、シャブージー、EJAEらが語る「ヒット曲誕生の瞬間」――映画音楽の創作秘話と「次のヒット曲」へのプレッシャー

「Golden」と『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が世界的な現象となってから、すでに4か月が過ぎた。チャートを8週連続で制し、ストリーミングは10億回を突破――その中心にいるのが、この曲の発案者でありメインボーカルを務めたEJAEである。だが彼女本人は、いまだに“同世代を代表するソングライターたち”と同じテーブルを囲んでいるという事実を信じきれない様子だ。
EJAEは「これは思いがけない幸運だわ」と、ヘイリー・ウィリアムスとシャブージーに挟まれながら語る。K-POPアイドル志望から今年まさかの大ブレイクへと至った紆余曲折の道のりを振り返りつつ、「急にスポットライトを浴びるようになって、本当に不思議な気分だ」と微笑む。
EJAEは今シーズンのオスカー有力候補として注目される6人のソングライターのひとりであり、米『ハリウッド・リポーター』恒例のソングライター対談に参加した。
11月の雨の土曜日、ウェストハリウッドのザ・サン・ローズで行われた1時間超の対談には、EJAEのほか、エド・シーラン(『F1/エフワン』『ズートピア2』の「Drive」「Zoo」)、ヘイリー・ウィリアムス(デヴィッド・バーンと共作した『The Twits -アッホ夫婦』の「Open the Door」)、ラファエル・サディーク(『罪人たち』の「I Lied to You」)、シャブージー(『The Long Walk(原題)』の「Took A Walk」)、そしてジャパニーズ・ブレックファストのミシェル・ザウナー(『The Materialists(原題)』の「My Baby (Got Nothing At All)」)が顔をそろえた。
このヒットメーカーたちは対談の中で深く踏み込み、最初に書いた曲の思い出から、ヒット後の“次作”プレッシャーの克服法、子ども向け楽曲の条件、さらには、ニューヨーク屈指の名門録音スタジオに潜む“謎めいた存在”が、今年最大級のヒット誕生に関与していたかもしれないという逸話まで、惜しみなく語り合ったのである。
――最近、自分が“これはヒットする”と思う頻度はどれくらいですか。最後にそう思ったのはいつで、実際にそうなりましたか。
エド・シーラン
いまは半々、ってところだと思う。自分がリリースする曲は基本的に気に入っているし、作っているときは“これはヒットするかも”と感じることが多い。とはいえ、実際のところはわからないんだ。これまで何度も驚かされてきた。
いまのライブセットで一番盛り上がるのは、じつは4年前にポケモンのために作った曲なんだ。当時はヒットとは言えなかったのに、気づいたら中央ヨーロッパのラジオで人気になっていてね。そんなふうに、思わぬところで火がつくことがあるんだ。
ヘイリー・ウィリアムス
いったい何が起きたの?
エド・シーラン
わからないんだ。あの曲は、ポケモンゲームをクリアしたときに流れるエンディングの曲でね。当時はまったく反応がなくて、ライブでも一度も歌わなかった。今年マドリードで公演したとき、客席に“あの曲を歌って!”と書いたボードを掲げている人がいて、試しに演奏してみたら、その夜で一番の盛り上がりだった。それでツアーでも歌うようになり、いまではライブでもっとも盛り上がる曲になっている。でも、ヒット曲だったわけではまったくないんだ。
ミシェル・ザウナー
私は、自分が書く曲は全部ヒットすると思い込んでいるのよ。でも現実がそうじゃないと、すごくがっかりする。(笑)
ヘイリー・ウィリアムス
その姿勢、すごく好きよ。
――エド、あなたは「Zoo」と「Drive」で大きなコラボレーションを果たしましたね。「Drive」から話を聞かせてほしいです。ジョン・メイヤーとの共作はどのようなものだったのですか。

エド・シーラン
ジョンと初めて会ったのは、僕が23歳のときだ。そこから、彼はある意味でメンターのような存在になった。ときどき“この曲でギターを弾いてくれない?”と頼むこともある。今回はブレイク・スラットキンと一緒にスタジオにいて、彼と僕とジョンの3人で作業していたんだ。ブレイクが『F1/エフワン』の音楽についてジェリー・ブラッカイマーから声をかけられていて、“僕が『F1/エフワン』のために歌ったらどう聞こえるんだろう?”って、全員が首をかしげていた。だって僕はアコースティックのイメージが強いからね。
でも、ジョンがあの印象的なフレーズを弾き始めた瞬間に流れが変わった。そのまま一気に書き上げて、すぐに彼らに送ったら、“OK”の返事が返ってきて、あっという間に映画に使われることになったんだ。
そして、もう一方にはシャキーラとの「Zoo」がある。こちらはサウンドの方向性がまったく違う。

エド・シーラン
シャキーラとは、奇妙なことにパンデミックの時期に知り合ったんだ。将来的に何か一緒にやろうと長電話を重ねて、細かいやり取りをしながら少しずつ制作を進めていった。「Hips Don’t Lie」の新バージョンを一緒に録ったりして、それがすごく楽しくてね。
EJAE
本当にすばらしかった。
エド・シーラン
映画のタイトルはイギリスでは『ズートロポリス(Zootropolis)』なんだけど、うちの子どもたちが大好きでね。娘は“自分はガゼルだ”って思い込んでいて、“ガゼルには曲が必要よ”なんて言うわけだ。だから“わかった、任せろ”ってことで、シャキーラと一緒に曲を書いたんだ。
5歳と3歳の子どもがいるから、僕は子ども向け映画をたくさん観ている。子どもの心に刺さる曲って、母音が中心になっているものが多いと思うんだ。だから“Zoo-ooh-ooh”みたいな響きになったんだよ。
ミシェル・ザウナー
「Golden」にも当てはまる気がする。子ども向けの曲とは言わないけれど、子どもたちは本当に好きだよね。
EJAE
メロディの力だと思う。子どもも好きだし、お父さんたちも好きなの。
シャブージー
再生してるのは大抵お父さんたちだしね。
EJAE
このあいだのハロウィンで、デーモン・ハンターズの衣装を着たお父さんを見かけたの。あれは最高だった。お腹の毛がもじゃもじゃのままクロップトップを着て、紫の髪にしているお父さんを見ると、本当にうれしくなる。すばらしいよ。
――脚本と完璧に噛み合うような“制約”がある中で、ヒット曲を書くのは難しくなりますか。
EJAE
私はK-POPの出身だから、細かい指示を受けて作ることには慣れている。だから、そうした作り方自体は自然だった。ただ、『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』はこれまでに例のないタイプの映画だったから難しかった。ミュージカルでもないし、MVやポップソングばかりの映画でもない。でも楽曲が物語を前に進めなきゃいけない。
「Golden」については、アーデン・チョーが声を務めたルミが“並外れた歌声の持ち主”という設定がまずあった。監督のマギー・カンは、歌が段階的にスケールアップしていくことで、彼女が“到底届かないように思える目標に手を伸ばす”という表現になるようにしたかったの。彼女には大きな重圧がかかっていて、登場人物たちは文字通り“彼女がその高音を出せるか”に運命を託している。それは“不可能な音”でなければならなかった。その音を作らなきゃいけなかったのは……まあ、私なんだけどね。

シャブージー
何テイクくらいかかったの?
EJAE
うわ……かなり多かったよ。もちろん難しかった。でもメロディ自体は、本当に驚くほど一瞬で出てきた。知ってるかわからないけど、あれは歯医者に向かう途中で浮かんだの。
――「運転中にメロディを口ずさみ始めた」と聞きましたが、本当ですか。
EJAE
そうそう。ソングライターって、ときどき“突然メロディが降ってくる瞬間”があるんだけど、あれはまさにそういう瞬間だった。締め切りが迫っていて、トラックだけ先にもらっていたんだけど、その日に曲を書き上げる必要があったの。で、歯医者へ向かう車の中で聴いたら“これはいい曲になる”ってすぐにわかったのよ。
最初に浮かんだメロディは “ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ、ナ” というもの。それをそのままボイスメモに録音したの。本当に、ボイスメモには足を向けて寝られないよ。

――皆さんの場合も、だいたいそんなふうに“突然降ってくる”ものなのですか。それともスタジオで意図的に引き出せるものなのでしょうか。
シャブージー
昨夜は夢の中で1曲できあがったよ。ときどき、夢の中でまるまる1曲作ってしまうことがあるんだ。
EJAE
覚えてるの?
シャブージー
ちゃんとスマホに録音した。朝早く目が覚めたあの“妙にハイな状態”のまま、急いでスマホをつかんで、夢の中で聴こえた通りに思い出して録らなきゃいけない。でも、ある程度近い形で記録できれば、あとはスタジオで仕上げられることが多いんだ。

エド・シーラン
マックス・マーティンも、ブリトニー・スピアーズの「ベイビー・ワン・モア・タイム」で同じような経験をしたと言っていた。彼の頭の中に突然メロディが降ってきて、“もう一度寝たい”って思ったらしいんだけど、頭の中で“いや、起きて録音しろ”っていう声が聞こえたんだって。で、彼は起き上がって曲全体を録音して、そのあとまたベッドに戻った。もしあの瞬間に起きなかったら……と思うと、ゾッとするよ。
僕は、スタジオには曲が宿っていて、有名スタジオはもうその曲を全部吸い取られてしまったように感じることがある。アビイ・ロード・スタジオに入ると、正直“もう残りのバイブスがない”と思ってしまうんだ。
ミシェル・ザウナー
全部吸い尽くされちゃったんだね。
エド・シーラン
だから僕たちはホテルの一室にスタジオを組んだり、家を借りて作業したりする。そっちのほうがずっとエネルギーがある気がするんだ。
ラファエル・サディーク
僕はスタジオに行く“プレッシャー”が好きなんだ。プレッシャーがダイヤモンドを生む、って言うだろ? アビイ・ロードに行けば、やっぱりビートルズのことを考える。「Let It Be」は作れなくても、何かしらひらめくかもしれないと思えるんだ。
EJAE
パワー・ステーションに行ったことはある?
ラファエル・サディーク
もちろんあるよ。
EJAE
私、「Golden」を録音してるときに、あそこで幽霊を見たんだ。

ヘイリー・ウィリアムス
ちょっと待って、それ詳しく聞きたい。
EJAE
私がいたのは4階だった。広いスタジオで、音量ノブがうまく作動しなくて。そういうときはアシスタント・エンジニアが確認に来るんだけど、エンジニアのサリーが入ってきた音がしたの。「あ、もう直ってるよ」って声も聞こえた。それで顔を上げたら、だれもいなかった。でもその0.3秒後くらいに、赤いフランネルシャツにブルージーンズを着た背の高い男性が、こっちに歩いてくるのが見えた。ほんの一瞬だったけど、見間違いではない。
シャブージー
それ、何て呼ぶか知ってる?「ゴーストライター」って言うんだよ。
EJAE
それは上手いね。でも本当に、その「ゴーストライター」はフランネルシャツとジーンズ姿で、私に向かって歩いてきたのよ。
ヘイリー・ウィリアムス
なんか……色っぽいじゃない。
EJAE
すごい状況だったのに、録音を続けなきゃいけなくて、まともに理解する暇もなかったの。でもその日、私はめちゃくちゃよく歌えた。音楽ディレクターにも「今日、何食べた?」って驚かれたくらいだよ。
ラファエル・サディーク
それ、幽霊が歌ってくれたんじゃないの?
EJAE
韓国ではね、録音中に超常現象が起きると、その曲はヒットするっていう言い伝えがあるんだよ。
ヘイリー・ウィリアムス
なるほど、証拠がここにあるってわけね。
――ソングライターにとって最大のプレッシャーは「最初のヒット」ではなく、「2曲目のヒットをどう生み出すか」だと言われますが、実際にその重圧を感じていますか。
EJAE
感じてるなんてものじゃない。一億万パーセント感じてるよ。本当に。信じられる?ものすごいプレッシャーだよ。韓国でもヒット曲は出してきたけれど、私の最終目標はずっと“ビルボードHot 100の1位を獲ること”だった。そのためにアメリカの出版社と契約したくらいで、心の準備はできていた。でも……うん、プレッシャーは尋常じゃない。
――シャブージー、あなたも似た状況ですよね。ブレイクした曲は“最多・首位獲得週”に並ぶ大ヒットで、次は“一体どうすれば再びそれができるのか”と期待されてしまいますね。
シャブージー
でも、いちばん大事なのは“楽しむこと”なんだと思う。あとは自分の直感を信じること。「Good News」――つまり「A Bar Song (Tipsy)」の次に出した曲だけど――あれを作ったときは、まさにその姿勢が大きかった。直感を信じて、楽しく作ること。そして、あれだけ大きな曲をひとつ出してしまうと、プレッシャーはありつつ、同時にどこか“解放”されるんだよ。“もう、これ以上何もしなくてもいいかもしれない”って思えるからね。
エド・シーラン
曲というのは、積み重ねていく“カタログ”みたいなものだと思う。大ヒットする曲もあれば、そこそこヒットするくらいの曲もあって、うまくいかない曲もある。でも、自分が全部気に入っていて、作り続けていれば問題ない。だって、僕たちの中でだれも音楽をやめるつもりなんてないだろう?
若い頃、よくエルトン・ジョンのウィキペディアを見ていたんだけど、彼は4曲連続でナンバーワンを取ったあと、次の5年間は浮き沈みが激しかった。それを見ると、すごく落ち着いた気持ちになれたんだ。
ミシェル・ザウナー
皮肉なことに、“前のヒットに続く何かを作ろうとしている”と、聴く人にはそれが丸わかりなんだよね。だから、自分自身に“落ち着いて”と言い聞かせるのが大事なの。でも、それがほぼ不可能なのよ。
結局いちばん良い曲っていうのは、“前に作った曲をまったく意識せずに”、前作と同じくらい純粋な場所から生まれてくるものなんだと思う。
ラファエル・サディーク
僕はビルボードなんて気にしたことがない。チェックすらしない。いい曲が書けたときは、自分でわかるんだ。

――ミシェル、あなたが書いた「My Baby (Got Nothing At All)」について、映画『The Materialists』(2025年)のセリーヌ・ソン監督は、参考にした曲としてジョン・プラインの「In Spite of Ourselves」とナターシャ・ベディングフィールドの「Unwritten」を挙げていました。
ミシェル・ザウナー
いやあ、ずいぶん幅広いよね。(笑)

――その2曲を提示されたとき、「なるほど、わかった」と思いましたか。それとも「どういうこと!?」と思いましたか。
ミシェル・ザウナー
セリーヌ・ソン監督とはZoomでとても良い打ち合わせができて、本当にラッキーだった。というのも、この曲は映画の特定の場面に当てるのではなく、エンドクレジットに流れる曲だったから、作品全体の“感情の総体”を包み込むことができる。だから、私はかなり自由に、自分がよく知っているテーマ「いつもお金のない人に恋してしまう」ということを表現できたの。
――ほかにも、参考にしたロマンティック・コメディの雰囲気はありましたか。
ミシェル・ザウナー
私は、とてもシンプルで、まっすぐ心に響くような感情を込めたかった。というのも、偉大なラブソングというのは、たいてい“ちょっとした言葉遊び”の上に成り立っていると思うから。しかも、そういう曲にはたいてい“ベイビー”という言葉が入っている。
だから、この曲にも“ベイビー”を入れたいと思ったし、“言葉のひねり”を使った感情表現にしたかった。それで生まれたのが “My baby is nothing at all” というフレーズなのよ。
――あなたの隣には、世代最高ともいえるラブソング作家が座っているわけですね。
エド・シーラン
いや、どうかな。というのも、僕自身は“ベイビー”って言葉を日常でまったく使わないんだ。妻のことを“ベイビー”と呼んだことなんて、一度もないと思う。
ミシェル・ザウナー
じゃあ、何て呼んでるの?
エド・シーラン
“Mooj”って呼んでるよ。
ヘイリー・ウィリアムス
その呼び名、歌に乗せたらどう?
エド・シーラン
わからないよ、マジで。でも、“響きがいい”ってだけで成立するんじゃない?
ミシェル・ザウナー
“Mooj”が?
エド・シーラン
いや、“ベイビー”のほう。
シャブージー
いや、“Mooj”も悪くないよ。
ミシェル・ザウナー
シングル曲「Mooj」のリリースが楽しみだね。
エド・シーラン
そもそも“Mooj”がどこから来たのかすら覚えてないんだ。ただ、そう呼び始めただけで……。
シャブージー
奥さんの名前は?
エド・シーラン
チェリーだよ。彼女も僕のことを“Mooj”って呼んでる。以前、車を買ったときに“シートに刺繍を入れますか?”って聞かれて、“じゃあMoojって入れて”って答えたんだ。いまは僕の警備担当がその車を使ってるんだけど、“Mooj”の刺繍はそのまま残ってる。まあ、話が脱線したね。
――ラファエル、「I Lied to You」について伺いたいです。あなたは以前、“The truth hurts, so I lied to you(真実は痛い。だから君に嘘をついた)”というフレーズを若い頃から持っていたと言っていましたが、これは曲のために温めていた言葉なのですか。
ラファエル・サディーク
いや、曲のためじゃないよ。若い頃からいつも使っていた言い回しなんだ。たとえば、もし彼女に嘘をついたのがバレたとするだろう?そのときに“ほら、真実は痛いって言うじゃないか。だから嘘をついたんだよ”って言い訳する、そんなジョークみたいなものだった。曲にするつもりなんて、その時点ではまったくなかったんだ。
――ずっと言い続けてきたそのフレーズを、“今回こそ曲にするべきだ”と判断したのは、どのタイミングだったのですか。
ラファエル・サディーク
僕はブルースが本当に好きでね。ブルースの曲って、タイトルがとにかくすばらしいんだ。ジョニー・テイラーには「Last Two Dollars」って曲があるんだけど、ああいう“言葉そのものに力がある”タイトルが昔から好きなんだ。
それで作曲家のルドウィグ・ゴランソンと一緒に仕事をすることになり、彼のスタジオに行ったら、彼が映画の話をいちから全部説明してくれた。ライアン・クーグラーもオークランド出身で、彼の父親と僕の兄貴がすごく仲が良かったんだ。だから自然とつながりができてね。

制作側から“求めるもの”の仕様を渡されたのが水曜で、彼らは土曜にもう撮影に入る予定だった。だから僕は聞いたんだ。“で、曲はいつまでに必要なんだい?”って。
シャブージー
きたね、プレッシャー。
ラファエル・サディーク
そしたら“今日中にお願いします”って言うんだ。“今日?”と聞き返したよ。そこで“自分のスタジオに持ち帰って作ってもいい?”と確認したら、“いや、できればいまここでやってほしい”と。どんどんエスカレートしていく感じだったね。
でもルドウィグはすばらしいコンポーザーであり、ギタリストでもある。彼と向き合って、ギターの短いフレーズから一緒に作り始めたんだ。
それから、完成した曲を映画公開の1週間前に観る機会があって、シーンにあまりにもぴったり合っていたのを見て驚いたよ。“言葉がここまで映像とはまることがあるのか”って、自分でも信じられなかった。

――ヘイリー、「Open the Door」について聞かせてください。あなたは昨年デヴィッド・バーンのソロアルバムで共作し、明らかに深い信頼関係を築いていましたね。そんな中で、今回『The Twits -アッホ夫婦』で再びタッグを組むことになった経緯を教えてください。
ヘイリー・ウィリアムス
デヴィッドはすでにしばらく前からサウンドトラックの作業に入っていて、制作側が“エンドクレジット用の曲が欲しい”と言ってきたの。私にはそんな依頼がよく来るわけじゃないし、しかも相手はデヴィッド・バーン。断る理由なんてどこにもなかった。
それに、私はいま“もっと自分にプレッシャーをかけなきゃ”と思っている時期だった。コロナ禍以降、家にこもりがちだったから、外に出て自分を成長させる環境に身を置くべきだと感じていた。でも、正直すごく怖かった。
当時住んでいた家の小さな地下スタジオで作業することになって、デヴィッドがやって来たの。実際に会ったのは過去に一度だけ。彼がアタッシュケースを持ってきて、キッチンカウンターに置いて、こう言ったの。『これ、50/50で分けようと思ってね』
シャブージー
そのアタッシュケースの中身って、何だったの?
ヘイリー・ウィリアムス
中には大量の書類が入っていた。ただの書類の山。
ミシェル・ザウナー
現金かと思った。
ラファエル・サディーク
『パルプ・フィクション』みたいにね。
ヘイリー・ウィリアムス
(笑いながら)そう、現金よ。“これがギャラだ”ってね。……冗談だけど。
それで地下に降りて作業を始めたんだけど、私は正直、自分がやれるのか不安だった。彼はすでに何曲かデモを送ってくれていて、そこには独特のトーンがあったし、物語の“核となるメッセージ”はしっかり理解できていた。だから“これが私の課題なんだ”と腹をくくれた。私は歌詞のほとんどを担当することになるとわかっていたからね。

デヴィッドは地下のスタジオでギターを弾きながら、コード進行の変化やフレーズを探っていった。その姿を間近で見られるなんて、本当に震えるほどすばらしかった。彼がちょっと指を迷わせながらラインを探す、その瞬間ですら学びになるんだ。
そんな彼が満足してくれて、しかも自分のヒーローとこんな体験ができたなんて――言葉にできないくらいうれしかった。
――シャブージー、「Took A Walk」はとても希望に満ちていて美しい曲ですが、映画自体は暗い。わずかな希望のきらめきはあるものの、『死のロングウォーク』は決して希望に満ちた作品ではないですよね。
シャブージー
僕は“意外性のある組み合わせ”が大好きなんだ。映画を観たときも“うわ、めちゃくちゃブッ飛んでる”って思った。でもおかしいのは、最初にスタジオに提案したのが“ジョニー・キャッシュの「I Walk the Line」をカバーしない?”だったことだよ。そしたら即答で“それはさすがに直球すぎる”って却下された。(笑)
映画を観てさらに確信したんだ。僕はスティーヴン・キングの大ファンで、昔は毎日違うキング作品を持ち歩いていた。読むためじゃなく、“自分にとって英雄がそこにある”というだけで力をもらえたからだ。そんなキングがキャリアで初めて書いた小説の映画化作品に、楽曲でかかわる機会を得たんだから、これはもう夢そのものだよ。スティーヴン・キング関連の作品に参加するのは、ずっと望んでいたことだったんだ。

――こうした出来事は、皆さんが大きな存在になればなるほど“些細なこと”のように感じられるようになってしまうのでしょうか。それとも、いまだに“こんなことが自分に起きるなんて想像もしなかった12歳の自分”を喜ばせる瞬間として残っているのでしょうか。
ヘイリー・ウィリアムス
正直に言えば、プレッシャーや自分の頭の中で渦巻く考えのほうが、何より私を小さくしてしまう。だからこそ、あえて“居心地のいい場所”だけにとどまらないよう自分を押し出し続けているの。
もちろん、ひとりで書くのは大好きだし、ベッドの中で作業するのがいちばんはかどる。でも、自分を一歩外に押し出して、その場所が安全で、美しくて――そして、ほんの少しでも“夢が叶っている”と実感できる瞬間があると、その経験こそが、また同じような機会へと向かわせてくれる。
シャブージー
“思い描いたものが現実になる瞬間”って、本当にすごいよね。あなたにとってのデヴィッド・バーンみたいな存在と実際に仕事ができるとか。
ヘイリー・ウィリアムス
あなたにとっては、スティーヴン・キングね。
シャブージー
そう、スティーヴン・キング。そして(EJAEに目を向けながら)君がK-POP界のスーパースターになったことも。
たぶん、このテーブルを囲む全員が“子どもの頃に願っていたことが、本当にいま、現実になっているんだ”と感じる瞬間を持っているはずだ。それって、本当にクレイジーなことだよ。
※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。

【関連記事】
- 伝説のライブ再び!テイラー・スウィフト『ERAS TOUR』最終公演が待望の映像化 ―― 圧巻のキービジュアル&予告編解禁、12.12にディズニープラス独占配信
- 【音楽伝記映画】エミネムからボブ・ディラン、ホイットニー:音楽史を彩る名作を厳選
- 坂本龍一ドキュメンタリー『Last Days 坂本龍一 最期の日々』が国際エミー賞を受賞|英国が最多7冠を達成
- エド・シーランが花嫁に!?新曲MVでルパート・グリントと14年ぶりの再共演
- Apple Music史上、最も再生された楽曲はエド・シーランの“Shape of You”-ドレイクやテイラー・スウィフトも大人気