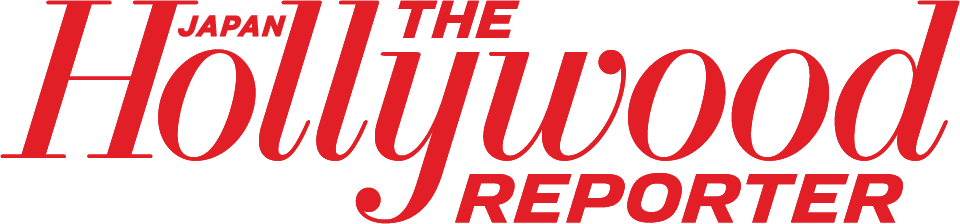Netflix世界1位!キャスリン・ビグロー最新作『ハウス・オブ・ダイナマイト』、米国防総省の批判にも「議論が生まれるのは喜ばしい」

キャスリン・ビグロー監督は、新作映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』をめぐる論争を歓迎している。米国防総省が、映画に登場する「アメリカの核ミサイル防衛システムの描写」を問題視し、内部メモで批判していたと米『ブルームバーグ』が報じたが、ビグローは「議論が生まれるのは喜ばしいこと」と米『ハリウッド・リポーター』の取材に笑顔で語った。
本作は、キャスリン・ビグロー監督と脚本家ノア・オッペンハイムが専門家への取材や綿密なリサーチをもとに制作。探知から核攻撃までわずか30分という極限状況で、政府当局がどのように対応するのかをリアルに描き出している。現在の米国防衛システムでは迎撃成功率が約50%とされ、劇中ではその不確実性を「コイントス(運任せ)」と表現している。一方、国防総省は「過去10年以上、試験では100%の命中率を維持している」と反論している。
しかし、この主張には異論も多い。『アトランティック』誌のトム・ニコルズは国防総省の見解を疑問視し、マサチューセッツ州のエドワード・J・マーキー上院議員らは「核問題への意識を高めた」として映画を称賛。国防総省の反応が議論をさらに白熱させる一方で、『ハウス・オブ・ダイナマイト』はNetflixで記録的ヒットを飛ばしており、配信開始からわずか3日間で視聴回数2,210万回を突破、映画部門で第1位に輝いた。
それでも、キャスリン・ビグロー監督とノア・オッペンハイムは騒動を前向きに捉えている。以下の米『ハリウッド・リポーター』との独占インタビューでは、2012年の監督作『ゼロ・ダーク・サーティ』で経験した論争から得た教訓や、今回の作品に込めた信念について語った。
**
――さっそく本題に入りたいと思います。キャスリンさん、『ブルームバーグ』が最初に報じた国防総省のメモについて伺います。それを知ってどのように感じましたか?
キャスリン・ビグロー(以下、ビグロー):とても興味深いことだと思います。理想的な世界では、文化が政策を動かす力を持つと思います。そして、もし核兵器の拡散について対話が生まれているのなら、それは私にとってとてもうれしいことです。
――国防総省が内々に映画に反応し、ミサイル防衛システムの描写に対して異議を唱えたことについて、どう感じていますか?また、なぜ彼らはそうした行動を取ったのだと思いますか?
ノア・オッペンハイム(以下、オッペンハイム):そのメモを書いた人たちの考えを推し量ることはできませんが、キャスリンが言ったように、政策立案者や専門家たちの間で「どうすれば世界をより安全にできるか」という議論が生まれていることを、私たちはとてもうれしく思っています。もしこの映画がそうした対話のきっかけになったのだとしたら、それこそが本作を作った理由のひとつですね。
――こうした動きによって、映画の信頼性が疑問視されることを心配していますか?国防総省が映画の描写に対して異なる立場を取っていることについて、どのように感じていますか?
オッペンハイム:私たちは、映画制作者と国防総省の間の議論だとは考えていません。むしろ、国防総省と、この分野のより広い専門家コミュニティとの議論だと思っています。たとえば、エドワード・マーキー上院議員や退役将軍のダグラス・ルート、『アトランティック』誌のトム・ニコルズ、記者のフレッド・カプランなど、この問題を長年取材してきた人たち、さらには非党派団体APS(アメリカ物理学会)などが、「現在のミサイル防衛システムは非常に不完全である」という映画の描写は正確だと述べています。
一方で、国防総省は「システムは100%の精度を誇る」と主張しているようです。私たちは、映画で描いた“コイントス(運任せ)”のような現状を指摘する専門家たちの言葉を信じていますし、こうして多くの人々が議論を交わしていること自体を喜ばしく思っています。

――国防総省は、製作時に彼らへ取材を行わなかったことも指摘しています。キャスリンさんは「本作は独立した立場を保つことが重要だった」とおっしゃっていますが、その理由を改めて教えてください。
ビグロー:私たちが実際に行ったように、さまざまな専門家に取材を重ねることが最善の方法だと思いました。この映画には非常に優れた技術顧問が参加してくれており、彼らが私たちの道しるべとなりました。
オッペンハイム:私は元ジャーナリストで、あなた(記者)もそうですよね。政府に所属していない人々のほうが、率直に意見を述べたり、正確な情報を提供してくれたりするものです。特定の政治的目的に縛られることがないからです。ですので、最近まで国防総省や情報機関、ホワイトハウスで働いていた人たちを取材し、彼らの証言を基に描いたことに、大きな自信を持っています。
――『ゼロ・ダーク・サーティ』のときも、政府関係者や専門家から多くの反応や議論がありました。そうした経験から、今回学んだことや気づきはありましたか?
ビグロー:私はただ「真実を描く」ことを心がけています。本作では、リアリズムと真実性を追求しました。それは『ゼロ・ダーク・サーティ』も『ハート・ロッカー』も同じです。『ハート・ロッカー』はもちろんフィクションですが、リアリズムを重視しています。
たとえば本作では、観客を米戦略軍(STRATCOM)の作戦指令室のような、通常は立ち入ることのできない場所に招き入れています。だからこそ、本物のように、誠実に描くことが重要でした。それが私の目標であり、達成できたと感じています。
――ノアさん、専門家たちのコメント以外に、Netflixでの配信開始後に寄せられた反応についてはどう感じていますか?
オッペンハイム:最も詳しい専門家たちから「非常に正確に描かれている」、「自分たちが長年研究してきた世界を見事に再現している」と言ってもらえたことは、本当にうれしかったです。
ビグロー:正直に言うと、核兵器についてはここ数十年、沈黙が続いてきました。この映画は、まさに今、必要とされていた対話を生み出すきっかけになったと思っています。
――『ハウス・オブ・ダイナマイト』はNetflixで配信されて以来、大きな反響を呼び、数日間トップの座を維持しています。やはり、長く沈黙に包まれていたテーマを扱っていることが共鳴を生んでいると思いますか?
ビグロー:その通りです。私たちは約1万2,000発もの核兵器に囲まれた世界に生きています。非常に危うい環境の中にいる――だからこそ、本作のタイトルは『ハウス・オブ・ダイナマイト』(=ダイナマイトの家)なのです。想像したくない現実に向き合い、理想的には核兵器削減に向けた議論を始めるべき時期に来ていると思います。
オッペンハイム:Netflixというプラットフォームの力には本当に驚かされます。世界中に一気に作品を届け、議論を広げることができるのです。配信からわずか数日でこれほど多くの人に観てもらえるとは、想像以上でした。アメリカだけでなく、世界各地でこの問題についての議論が起きています。
私の元同僚の記者仲間や海外の友人、家族からもメッセージが届き、「キャスリン・ビグローはやっぱりすごいスリラーを作る」、「2時間ずっと緊張しっぱなしだった」と言われる一方で、「こんな重要な政策課題について考えるのは久しぶりだ」といった声も多く届いています。その両方を感じてもらえたことが何よりうれしいです。
――キャスリンさんにとっては、本作が初の配信映画になります。SNSなどで反応を追っていますか?
ビグロー:(笑)世界中からテキストやメールが届いています。本当に感動的です。配信の広がりはすばらしいですが、それ以上に、作品そのもの――物語やテーマが議論を生み、建設的な緊張感をもたらしていることが何よりうれしいです。つまり、ようやくこの話題が公の議論になったということです。2月には新たなSTART(戦略核兵器削減)条約の交渉が始まりますが、その交渉に関わるという方から「映画を2回観た。交渉に良い影響を与えたい」とのメッセージも届きました。
――ラストシーンについては、あえて観客に不確かさを残したことが多く議論されていますね。その反応をどう見ていますか?
オッペンハイム:キャスリンと私は、観客がエンディングで考え、対話を続けてくれるような映画にしたいと思いました。安易に答えを示したり、きれいに締めくくったりするのではなく、むしろ深く考えるきっかけを作りたかったのです。Netflixがキャスリンのビジョンを最初から尊重してくれたことにも感謝しています。エンディングが議論を生み出しているのは、まさに私たちが願っていたことです。
ビグロー:私はいつも作品を「問い」から始める傾向があります。『ハート・ロッカー』では「イラク戦争が最も激しかった時期に、反乱勢力はどのような戦術をとっていたのか?」という問いから始まりました。『ゼロ・ダーク・サーティ』では「なぜオサマ・ビンラディンを見つけるのに10年かかったのか?」でした。そして今回の作品もまた、映画自体がひとつの問いを提示し、それに対して観客が自分なりの答えを導き出すための機会を提供しているのです。
**
映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』は、Netflixにて独占配信中。
※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。編集/和田 萌

【関連記事】
- 米国に迫る核の危機…映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』予告解禁、Netflixで10月24日より配信
- Netflix最新作『ハウス・オブ・ダイナマイト』『フランケンシュタイン』『ジェイ・ケリー』──先行劇場公開でスクリーンに登場
- 【Netflix】2025年11月のおすすめ配信作品 ―― 岡田准一主演『イクサガミ』、『ストレンジャー・シングス』シーズン5ほか
- Netflix映画『フランケンシュタイン』本予告が解禁 ── ギレルモ・デル・トロ監督の名作&おすすめ関連作も紹介
- 【ハリウッドの政治映画20選】衝撃作『ゲット・アウト』ほか、権力やアメリカ政治を問う傑作を厳選!