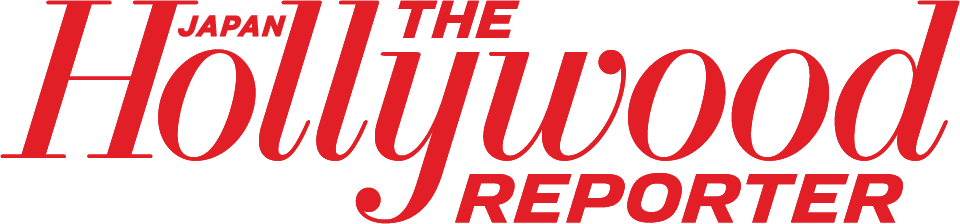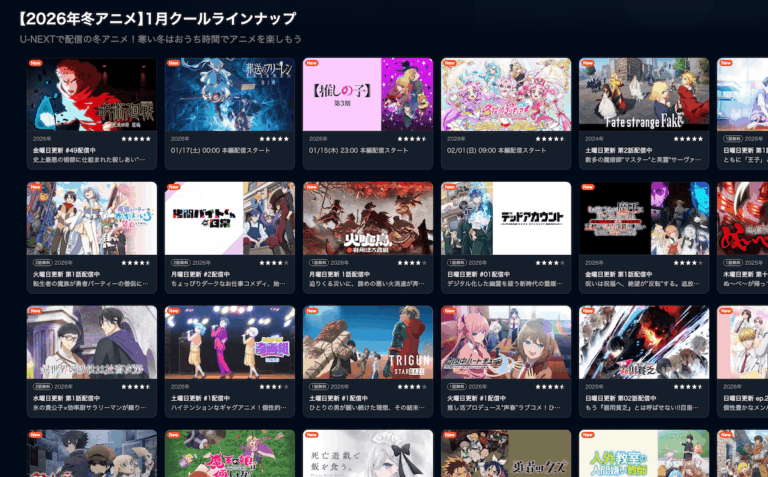『シビル・ウォー』と選挙ストレス:政治的芸術の議論とアメリカの未来を考察

アレックス・ガーランドの最新作が賭けの対象を十分に明示しているかどうかをめぐる議論が続く中、THRの2人の批評家は、特に緊迫した選挙の年における政治的な芸術の重荷について考察する。
『シビル・ウォー』、選挙ストレス、政治的芸術:批評家たちの議論
デビッド・ルーニー:アメリカ史上最も論争の的となっている選挙の年の中盤に差し掛かろうとしている。激しい分断によって、「アメリカ合衆国」という呼称がますます時代遅れになっているのを嘲笑している。人々は、一方の側の怒りを煽り、暴力を引き起こす可能性のある大統領選の投票を前に、不安を感じている。
このような状況は、アレックス・ガーランドの『シビル・ウォー』にとって理想的なタイミングのように思える。この映画は、初週末の2570万ドルの興行収入でA24の記録を更新し、2週目もNo.1の座を守った。この数字に異論を唱えることはできない。しかし、もっと興味深いのは、この映画のあいまいな政治姿勢が逃げ口上なのかどうかをめぐって、この映画が巻き起こした議論だ。
おそらく近年最もアメリカ礼賛の映画である2022年の『トップガン マーヴェリック』では、爆撃が必要なウラン濃縮工場を持つ外国の敵は、36年前の続編の原作と同様に、せいぜいあいまいな言及でしか特定されていなかった。これを、国際市場を疎外しないようにするための、スタジオの経理担当者による戦略的な選択だと想像するのは難しくない。
ガーランドの動機はおそらくそれほど皮肉ではないが、『シビル・ウォー』に対する主な批判の1つは、この映画が – カースティン・ダンストの心に残る演技とともに内臓的な力強さで監督された – 扇動的な近未来の悪夢を設定しながら、戦線を明確にすることを拒否しているというものだ。確かに、ファシスト的な大統領が在任しているが、これは2024年の多くのアメリカ人が抱いている恐怖だが、正確に誰が誰と戦っているのだろうか?
映画の冒頭数分で、私たちは、ウェスタン軍と呼ばれる軍事化された部隊が、カリフォルニアとテキサスの分離主義同盟のために戦っていることを知る。このありそうもない連合は、これが今日のアメリカではないことを告げているようだ。それは、アメリカの政治的風景の標準的な赤/青の二項対立を、多くの人が今こそ必要だと解釈しているイデオロギー的な一貫性の欠如とともに、あいまいに退けているのだ。
映画『シビル・ウォー』とアメリカの分断
『シビル・ウォー』は、トランプ政権の2期目が明確な可能性である私たちの危うい瞬間に、政治的芸術における謎かけの適切な時期なのかという疑問を投げかけている。
ロヴィア・ギャーキー:『シビル・ウォー』への反応で印象的なのは、それがいかに道徳的な明快さと方向性に対するこの国の不安な欲求を反映しているかということだ。人々は常に芸術に投影してきたが、芸術が私たちにどう生きるべきか、何をすべきかを教えてくれることへの新たな絶望があるようだ。私は、ポップカルチャーが政治の理解と認識を交渉するための重要な空間だと信じているので、これらの会話には価値があると思う。しかし、芸術は政治教育の代わりになるだろうか?
私は、『シビル・ウォー』で最も強烈なシーンは、リー(ダンスト)とジョエル(ワーグナー・モウラが涼しげな魅力で演じている)がニューヨークの警官と市民の対立を取材しているシーンだと認める。ほとんど台詞はないが、賭けは明確だ。人々は水を要求し、国家は警官に代表され、それを妨害している。このシーンは、最近のデモでますます馴染み深くなっているイメージ、つまり法執行機関と市民の間の状況が不安定になる場面を再現している。これは強烈で明示的な瞬間だ。
しかし、他の場面では、この映画のあいまいな反戦の立場に悩まされた。それは、国家的にも地政学的にも不十分に感じられるのだ。戦争は悪いが、他に何があるのか?
『シビル・ウォー』は、アメリカ人に迫り来る破滅を警告することに熱心だが、悪を名指しすることは望んでいない。テキサスとカリフォルニアが同盟を組むという現実世界のタイムラインもあるかもしれないが、そのシナリオをもう少し肉付けしてもらえればありがたい。この実現可能性を生み出している政治的現実とは何なのか?もちろん、その質問に答えることは、一部の視聴者を不快にさせるかもしれないが、それは底辺にとってはよくないだろう。
ルーニー:ここで思い出したのは、最近発表されたブロードウェイでの「ロミオとジュリエット」の上演予定で、レイチェル・ゼグラーとキット・コナーが主演することになっているが、演出家のサム・ゴールドは、「11月の大統領選を控えて、若者が感じている世界への怒りを称え、希望を祝う作品を今秋に作りたいと思った」と語っている。この作品のキャッチコピーは「若者はクソだ」というもので、特定のターゲットに向けられたものではなく、おかしくなった世界に向けられた世代間の怒りが沸騰していることを示唆している。
政治的芸術の意味とその限界
そして、それこそが、誰もが50対50に二分された国の一方の側に立つことで観客を減らしたくないと思っている時代に、私たちが消費することになるかもしれない、あいまいな政治的芸術なのだ。
ギャーキー:今日の主流の政治的芸術のあいまいさを考える際、経済的動機を無視することは難しい。その意味で、私は『シビル・ウォー』は世の中にあるものの多くと歩調を合わせていると思う。本質的にリスクを招く人種風刺のようなサブジャンルを見てみよう。私は最近、『アメリカン・ソサエティ・オブ・マジカル・ニグロス』や『アメリカン・フィクション』のようなオスカー受賞作品が、スパイク・リーの『バンブーズルド』やイヴァン・ディクソンの『The Spook Who Sat By the Door』のような過去の比較可能な映画を非常に鋭く刺激的にした、あの種の痛烈な風刺を決して提供しないことについて書いた。
この会話を音楽まで広げると、ビヨンセの『カウボーイ・カーター』には私が楽しめるところがたくさんあるが、アルバムのより広い国家的政治への関心は表面的なものにすぎない。アメリカの破れた約束へのより広い批判を示唆する瞬間があるにもかかわらず、アーティストの関心は主に彼女の批判者を論破することにあるようだ。
こうした作品の一部は、15年前、10年前、あるいはわずか5年前なら、もっと先鋭的で力強く感じられたかもしれない。オバマ大統領の当選の余韻の中で、あるいはトランプ氏の露骨な不道徳の影の中でだ。当時は、選出された政治家が有権者の利益のために行動していると信じるアメリカ人の方が多かった。今日、国家が多くの点でコミュニティから撤退しているという考えが説得力を増している。COVID-19のパンデミックへの対応、企業が煽るインフレ、そして最近ではガザ地区での永続的な停戦を求めることを拒否した米国の対応は、幻想を打ち砕いた数多くの事柄のほんの一部に過ぎない。今日の芸術は、主流であっても、少なくとも何が起きているのかを名指しする必要があるという議論の余地がある。
本物の政治的芸術は存在すると思うが、注目を集めるのに苦労している。それは、大多数の視聴者が賛同できるような漠然とした陳腐な表現を示すのではなく、現在のシステムが人々にどのような影響を与えているかに立ち向かう作品だ。サヴァナ・リーフの2023年の映画『Earth Mama』のような静かな作品は、現代の養子縁組の人種的・社会経済的な層を観察しているし、ヴェラ・ドリューの『The People’s Joker』のような大胆な作品は、大切な知的財産を覆して衝撃的なクィアのビルドゥングスロマンを作り出している。どちらの映画も、政治をキャラクターの生活の一部として扱っており、避けるべき失礼な話題ではない。
ブロードウェイで公開されたばかりのピーター・モーガンの『Patriots』も、もう一つの説得力のある例だ。この作品は、ウラジーミル・プーチンの権力への道のりに重要な役割を果たしたロシアのオリガルヒ、ボリス・ベレゾフスキー(マイケル・スタルバーグ)の活気のあるドラマチックな肖像画だ。眠たくて不器用に説明的な第1幕は、電気を帯びた第2幕につながっていく。モーガンは、これらの力を持つ男たちの関係を利用して、エリートのための代理戦争としての政治について身の毛もよだつ結論を導き出す。
ルーニー:ここに書かれたことすべてに同意しますが、私が提供できる世代的な見方があるのではないかと思います(つまり、私は年寄りなのです!)。ジョナサン・デミの『フィラデルフィア』というAIDSドラマが1993年に公開された際、ゲイの観客の一部は憤慨しました。トム・ハンクスとアントニオ・バンデラスが演じるカップルの愛情表現が、年老いたおばさんの頬にキスするようなおとなしいものだったからです。『ブロークバック・マウンテン』も、ヒース・レジャーとジェイク・ギレンホールが演じる苦しむ関係のセクシャリティを控えめに描いたとして批判された作品です。
こうした主流の作品や、ゲイの活動家で政治家のハーヴェイ・ミルクの暗殺を描いたガス・ヴァン・サントの『ミルク』などは、LGBTQ問題(AIDSを含む)や権利(同性婚を含む)が問題になっている時期に、十分に大胆でなかったり、十分に同性愛的でなかったり、十分に政治的でなかったりすると非難されることがよくあります。
しかし、振り返ってみると、これらの映画が会話を進めたことは否定できません。おそらく、かなりの割合のアメリカ人は、同性婚の考えを受け入れるのに十分な心の準備ができるまで、過激というよりは人間的な『Will & Grace』のようなテレビ番組を必要としていたのかもしれません。
振り返ってみると、アン・リーがアメリカの男らしさの最も永続的なシンボルである2人のカウボーイの間のゲイのラブストーリーを描いたことには、大胆さ、そして政治性がありました。一部の道徳的なストレートの男性は激怒しましたが(アーネスト・ボーグナインは有名なアカデミー会員の試写を拒否しましたが)、十分な観客が映画を受け入れ、1400万ドルの製作費で世界中で1億7800万ドルの興行収入を上げるグローバルヒットになりました。
『ブロークバック・マウンテン』がアカデミー賞作品賞を獲得するまであと一歩だったこと(『クラッシュ』の大失敗の話はやめておきます)は、10年後の『ムーンライト』の受賞への道を開いたのかもしれません。バリー・ジェンキンスの不朽の名作は、クィアな黒人男性という繊細な主題を、謝罪なき率直さと官能性で扱いました。これは、おそらく10年前の大作では考えられなかったことでしょう。
私が言いたいのは、政治的な芸術は少しずつ力を発揮できるということです。もしかしたら10年後には、『シビル・ウォー』を振り返り、戦線があいまいであっても、反乱と毒を含んだ分極化というアメリカの醜い現実を見据えた、毅然とした写真のようなものだと認識するかもしれません。
ギャーキー: あなたのクィア映画についてのコメントは、ここで政治的芸術とは何を意味するのかを考えさせてくれます。すべての芸術は、ある程度、政治に影響を受けています。昨年、クリストファー・ノーランの『オッペンハイマー』とマーティン・スコセッシの『Killers of the Flower Moon』は、核兵器を落とすという決定から先住民コミュニティの大量虐殺まで、アメリカの残虐性の亡霊に立ち向かいました。過去を振り返ることは常に後知恵の明快さを提供するので、これらの映画の議論は認識と贖罪に焦点を当てていました。現代の道徳的退廃を認識するよりも、過去について後悔するほうが簡単なのかもしれません。(ジョナサン・グレイザーのオスカー受賞スピーチに人々がどのように反応したかを見てください。)
そして、アヴァ・デュヴァーネイの『Origin』は、愛と悲しみの物語として最も痛切に機能していると思いましたが、この映画は根本的に政治に関係しています。イザベル・ウィルカーソンの『Caste』にインスパイアされています。『Caste』は、アメリカにおける人種を理解するための新しい枠組みを提示する知的な大作です。そして、もちろん『Barbie』もありました。アメリカ・フェララの評判の高い独白は、私にはそれほど魅力的ではありませんでしたが、現代のフェミニスト政治の基本的な入門書を多くの視聴者に提供したことは間違いありません。
最近の小さな映画、ショーン・プライス・ウィリアムズの『The Sweet East』(タリア・ライダー、ジェイコブ・エロルディ、アヨ・エデビリ主演)は、今日の愛国心のアイデアと格闘しました。『不思議の国のアリス』のような物語構造により、無政府主義グループから極右派まで、アメリカの生活の異なる一面を調査することができます。『シビル・ウォー』と同様に、結果は時に浅く感じられますが、今のこの国の姿を捉えようとする野心を否定することはできません。
ルーニー: 今のこの国の姿を、少なくとも1、2時間は忘れたいと思っている人たちはどうでしょうか?不確実な時期に観客が気を紛らわそうとするのは、今回が初めてではありません。大恐慌時代に栄えた映画を思い浮かべてください。コメディ、ミュージカル、メロドラマなどです。バスビー・バークリーの映画のカレイドスコープのようなファンタジーのナンバーほどエスケープできるものはありません。
2つのおすすめを紹介しましょう。パトリシア・ハイスミスのスリラーを巧みに脚色したNetflixの『リプリー』は、脚本・監督のスティーブン・ザイリアンと優れたキャストによって、高いスタイルで語り直され、選挙の不安をすべて忘れさせてくれる約8時間のサスペンスを提供しています。同じくルカ・グァダニーノ監督の『Challengers』の爽快なエネルギーとセクシーな楽しさも、砂漠で長い間過ごした後にオアシスに出くわしたような感覚です。誰かがこの絶望的に分断された国家を団結させることができるとしたら、それはおそらくゼンデイアでしょう。
※本記事は英語の記事から抄訳・要約しました。
【関連記事】
- 興行収入:「シビル・ウォー」が新作ヴァンパイア映画「アビゲイル」と首位争いを繰り広げる
- A24『シビル・ウォー』レビュー:近未来のアメリカを描く“曖昧な”ディストピア映画
- A24新作『シビル・ウォー』、記録的な北米興収で初登場1位!