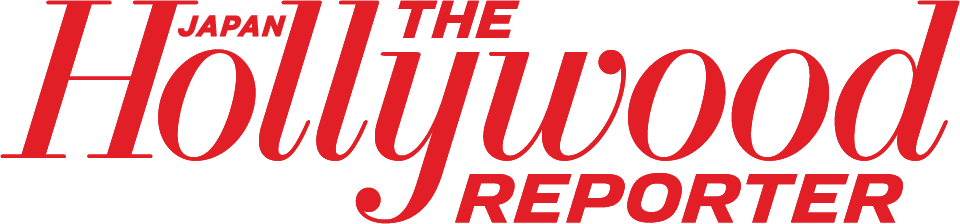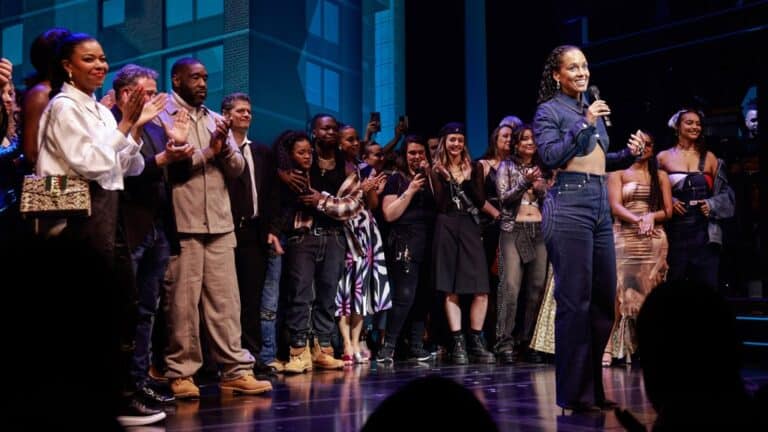カンヌ注目作『ルノワール』 早川千絵監督が語る子どもとの協働【インタビュー】

映画監督・早川千絵が、2022年に発表した長編デビュー作『PLAN 75』で国際的な注目を浴びた。同作は、高齢者を対象とした国家主導の安楽死制度を描いたディストピア作品であり、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品された。さらに、カメラドール特別表彰を受けたことで、早川は世界の映画界にその名を刻んだ。節度ある演出と人間の弱さを見つめる眼差しが高く評価されている。
それから3年後、早川監督は新作映画『ルノワール』を携え、カンヌのコンペティション部門に初めて登場する。本作は、1987年の東京郊外を舞台に、11歳の少女・フキの視点から描かれる感情豊かな成長ドラマである。父が末期がんで倒れ、家族が静かに崩壊していく中、フキはテレパシーやオカルトに惹かれ、見えない力で周囲の断絶をつなごうとする。
『PLAN 75』が明確なコンセプトに基づいて構成された寓話的作品であったのに対し、『ルノワール』は早川監督の個人的な記憶と感情の断片をもとに、自然発生的に物語を紡いだ作品である。自身の幼少期に父をがんで亡くした経験が、本作に強く反映されている。
早川は「子ども時代を思いやりを持って見つめ直し、孤独や混乱、わがままさを受け入れつつ、自分を許し、人とつながる方法を探したい」と語っている。
舞台となる1987年は、日本がバブル経済の絶頂期にあった時代である。物質的な豊かさの陰で精神的な空洞が広がっていたこの時代背景は、フキの孤独や葛藤をより鮮明に浮かび上がらせる。早川監督は「人々が繁栄に酔いながらも、内面では深い孤独を感じていた時代。静かに壊れていく人間のもろさを描きたかった」と述べている。
タイトルの『ルノワール』は、フキが父に買ってほしいとねだるルノワールの絵画《イレーヌ嬢》に由来する。実際に早川監督の父も同じ複製画を幼少期の彼女に贈っており、その記憶が物語に結びついている。1980年代の日本では、西洋文化への憧れの象徴として、ルノワールの複製画が家庭に飾られていたという背景もある。
映画『ルノワール』は、東京を拠点とするローデッド・フィルムズが製作。『PLAN 75』に引き続き、撮影監督・浦田秀穂、音楽・Rémi Boubal(レミ・ブーバル)、編集・Anne Klotz(アン・クロッツ)といった早川監督の信頼するスタッフが再結集している。主演は新人の鈴木唯。11歳(撮影当時)とは思えないほど繊細で力強い演技で観客を魅了する。そのほか、リリー・フランキー(『万引き家族』『そして父になる』)や石田ひかりといった日本の実力派俳優が脇を固める。
『ルノワール』は、早川千絵がこれまでに築き上げた表現力と、個人的な記憶に根ざした新たなアプローチが融合した、非常に注目度の高い作品である。世界最大級の映画祭であるカンヌ国際映画祭でのプレミア上映を控え、世界の映画ファンと批評家の関心が高まっている。
『ルノワール』に込めた想いや制作背景について、早川監督はどのように語ったのか。米『ハリウッド・リポーター』は、その世界初公開を控え、日本にいる早川千絵監督にインタビューを行った。
――『ルノワール』の着想やアプローチはどこから来たのでしょうか?
前作『PLAN 75』は、非常に明確なコンセプトに基づいて構成されていました。「映画でしか語れないことを表現したい」という気持ちがありました。でも『PLAN 75』が完成してから、たくさんのインタビューで作品の前提や、日本の社会的背景について何度も何度も説明しなければならなかったんです。それが少ししんどくなって、自分の説明が本当に正しいのか疑問に思うこともありました。だから今回は違うアプローチをしてみようと思ったんです。最初から明確なビジョンがあるのではなく、むしろ何も決めずに始めたら、自分はどんな映画をつくるのだろう?と。
今回はコンセプトや社会問題からではなく、もっと感情的な部分を起点にした作品にしたかったんです。脚本を書き始めた時は、10代の頃から頭の中にあった小さなエピソードの断片をただ書き出しただけで、それらはまったくつながっていませんでしたし、強いコンセプトも前提もありませんでした。

――物語をどのように構築していったのですか?
本当に難しかったです。最初はもっとたくさんの登場人物が出てくる構想でしたが、少しずつ削ぎ落としていって、最終的には1人の少女のひと夏の物語に絞られていきました。でも、最初の段階ではテーマもはっきりしていなかったし、脚本を書いている時も、撮影している時も、まだ確固たるものは見えていませんでした。編集段階になって、ようやく「これは、他人に思いやりを持てなかった少女が、痛みを知ることで一歩だけ大人に近づく話かもしれない」と思い至ったんです。その痛みの描写が、バラバラだったエピソードをつなぎ合わせていくうちに、自然と浮かび上がってきた。
まるで粘土で彫刻を作っているような感覚でした。何を作っているのか自分でもわからないけれど、形にしていくうちに、ようやく輪郭が見えてくる。そんなプロセスでした。
――物語の意味が見えないまま映画をつくるのは、かなり勇気のいることだったのでは?
すごくストレスでした(笑)。でも、その分、楽しかったです。最終的にどんな作品になるのか、自分でも全然わからなかったので。自信をなくす日もあれば、ただただ「どうなるのか楽しみだな」と思う日もあって。撮影初日には、スタッフ全員を集めて「正直、この映画が良くなるのか自信がありません」と伝えたくらいです。でもチームや俳優たちと一緒に作業をしていくうちに、「これはすごく力強い作品になるかもしれない」と感じられるようになりました。それでも、最後まで全体像は見えていなかったので、ずっとワクワクしていましたね。
――主演の鈴木唯さんについてお聞きします。とても自然体で、圧倒されました。彼女をどのように見つけたのですか?
フキのキャスティングはこの作品で最も重要だと考えていたので、何百人もオーディションする覚悟でした。でも、唯ちゃんが最初に来たんです。彼女は日本のインディペンデント映画祭で上映された、ある大学生の映画に出演していて、その作品の英語字幕をうちのプロデューサーの一人が担当していたんです。また、別のプロデューサーはその映画祭の審査員を務めていて、二人とも「彼女は本当に素晴らしい」と強く推薦してくれました。それで唯ちゃんを呼んでオーディションしたら、すぐに「この子かもしれない」と感じました。
でも彼女が一人目だったので、「こんなに早く決めていいのか?」と思って、それから何十人もオーディションしました。でもずっと唯ちゃんのことが頭から離れなかった。1~2か月後、「やっぱり唯ちゃんしかいない」と決めました。
――子役と一緒に仕事をするのは初めてだったそうですが、どんなふうに接したのでしょうか?とても繊細な演技でした。
そうなんです、子役と仕事をするのはこれが初めてでした。唯ちゃんは赤ちゃんの頃からモデルをやっていたので、カメラの前でも全く緊張しない。あるとき彼女に「自分の得意なことは何?」と聞いたら、「動物のモノマネが得意です」と答えて、馬とか猫とか羊とか、本当に見事な鳴き声を披露してくれました。それを聞いてすぐに脚本に書き加えました。彼女から受けたインスピレーションはとても多く、彼女に合わせて物語も少しずつ変わっていったんです。
子どもとどう接するべきかについて、私はたくさんの本を読んだり、他の監督のインタビューを読んだりしました。脚本通りにやる人もいれば、完全に即興に任せたり、時には子どもを泣かせるような演出をする人もいる。でも私は、彼女をきちんとした“協働者”としてリスペクトしたいと思いました。もう11歳(撮影当時)ですし、自分が関わっている作品の意味をある程度理解していてほしいと思ったんです。だから、物語や映画のスタイルについて、できる限り説明しました。
ただ、私自身もまだ全体像をつかみきれていなかったので…。この作品で最も大きな影響を受けたのは、スペイン映画の『ミツバチのささやき』(ビクトル・エリセ監督)です。だから唯ちゃんにもDVDを渡して、「この映画を観てみて。私たちが作ろうとしているのは、日本のテレビでよく見るような作品とは全然違うんだよ」と説明しました。
――彼女(鈴木唯)の反応はどうでしたか?
彼女にとっては初めて観る外国映画だったそうで、観る前はちょっと怖かったみたいです。でも、「すごく好きだった」と言ってくれて、「ちょっと難しいところもあるけど、子どもの気持ちを理解しようとしてる映画なんだなって思った」と言ってくれました。それがすごく嬉しかったです。
――撮影現場では彼女とどうやって一緒に仕事をしたんですか?
リハーサルや撮影が始まってみてすぐに、「あ、この子には細かい演出はいらないな」って思いました。私が伝えるのは、「こういう状況で、こっちに歩いて、ここに座って」っていう本当にシンプルなことだけ。感情の出し方とか、顔の表情とか、そういうことはほとんど何も言いませんでした。彼女はとても自然体で、まるで自分自身のやり方でその“彫刻”に粘土を加えてくれるような存在でした。次第にすごく信頼するようになって、完全に頼りにしていました。まさに「アーティスト」ですね。
――『PLAN 75』とは違う作品を目指したとおっしゃっていましたが、それでも主人公に共通点を感じました。特に『PLAN 75』の後半に出てくる倍賞千恵子さんのキャラクターと、どこか共鳴しているように感じました。どちらも、世界との関わり方に“存在の静けさ”や“感覚的な喜び”があるように思えて。
そうですね、確かに『PLAN 75』の主人公と、今回のフキには共通点があると思います。どちらも一見すると受動的に見える存在で、周りの人や状況をただ静かに受け止めているような。でもそこに強い感情や魂が確かにあるんです。そういう意味では、確かに繋がっている部分があると思います。もちろん、どちらも私自身が書いたキャラクターなので、ある種の共通した感性はあるんでしょうね。
――個人的な感想ですが、鈴木唯さんがちょっと若い頃の監督に似ているなと感じたんです。見た目だけじゃなくて、雰囲気や佇まいも。自分自身の“アバター”のような存在として見ていた部分はありますか?
(笑)うーん、そういうふうには考えていませんでした。キャスティングのときに一番大事にしていたのは、「人を惹きつける力」があることでした。必ずしも“美人”である必要はないけれど、なぜか目が離せない、というような魅力。私に似てるかどうかは全然意識してなかったんですけど、撮影中にスタッフから「フキちゃん、監督にちょっと似てますね」って言われたことはあります。でも、どちらかというと、私の方が彼女に影響されて真似してしまってたかもしれません。撮影中はずっとモニターで彼女を見ていましたから、表情とか無意識に真似しちゃうことってあるじゃないですか?たぶん、それに近い感じだったと思います。
――映画を観ながら何度も思ったのは、「子どもはとても強く物事を感じ取るけれど、それを言葉にしたり理解する枠組みがまだない」ということでした。だからこそ夢のシーンを使ってフキの内面に入っていくやり方がすごく心に響いて…。冒頭では彼女はまだ痛みや寂しさに無自覚で、悪夢を見たりする。でも、ラストでは先生に優しくハグされて、浜辺で楽しい時間を過ごしたあと、きらびやかなパーティー船の夢を見る。まさに子どもが見るべき夢ですよね。質問ではないのですが、本当にその描写が美しくて、思い出すだけで涙が出そうになります。
そんなふうに受け取ってもらえて、すごく嬉しいです。実は、夢のシーンについては「なんでこれが入ってるの?」「どういう意味?」って聞かれることが多くて…。だから、そういうふうに感じてくれた人がいるというのは、本当に安心しました。
――監督ご自身は、日本の“ヒューマニズム的”な映画の系譜に連なる存在だと感じますか?カンヌでは是枝裕和監督と比較されることもありそうですが。
そうですね、やっぱり是枝さんの名前は出てくるだろうなと思います。テーマ的にも、子どもが中心にいるという点でも。実際に、是枝さんの作品からは影響を受けています。高校生のときに作品を観て、大好きになりました。今回、リリー・フランキーさんにも出演していただいたのですが、彼も是枝組の常連ですしね。
でも、それ以上に今回の作品に大きな影響を与えたのは、相米慎二監督の『お引越し』です。あの作品のことは本当に何度も思い出しながら作っていました。撮影前には撮影監督とも話して、相米作品の他に『ミツバチのささやき』(ビクトル・エリセ監督)や、エドワード・ヤン監督の『ヤンヤン 夏の想い出』についても意識しました。いくつかのシーンには、そうした作品からの直接的な影響もあると思います。
――『PLAN 75』でカンヌの「ある視点」部門に選ばれてから3年、今回はメインコンペティション入りです。カンヌの“ファミリー”の一員になりつつあるとティエリー・フレモー(カンヌ国際映画祭の総代表)も言っていましたが、今の心境はいかがですか?
他の素晴らしい監督たちの名前と一緒に自分の名前があるのを見たときは、本当に現実感がなかったです。もちろん光栄ではあるんですけど、今はまだ「変な感じ」というのが正直なところです。本当にまだ実感が湧いていないですね。
今回、インタビューに応じてくれた早川千絵監督作『ルノワール』は2025年6月20日より全国の劇場で公開予定。
この記事は要約・抄訳です。オリジナル記事はこちら。
【関連記事】
- 映画『ルノワール』レビュー:早川千絵監督作、孤独と向き合う少女の繊細な心の軌跡
- 早川千絵監督『ルノワール』カンヌで世界初上映「熱気が段違いで胸がいっぱい」
- 【カンヌ国際映画祭2025】日本人監督の過去作品をご紹介!早川千絵監督『PLAN 75』ほか
- 松居大悟監督、杉咲主演で金原ひとみ氏の『ミーツ・ザ・ワールド』映画化
- 奥平大兼『か「」く「」し「」ご「」と「』をアピール「自分に当てはめて見て」